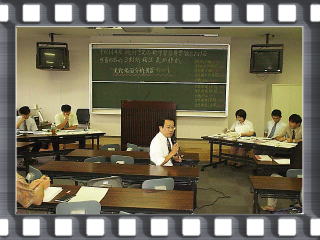 まさにディベートが始まります!
まさにディベートが始まります!記:2001年7月12日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
第2回目のディベートが行われました。今回は、「平成14年度施行の新学習指導要領に
おける学習内容の3割削減は是か非か」という論題でした。
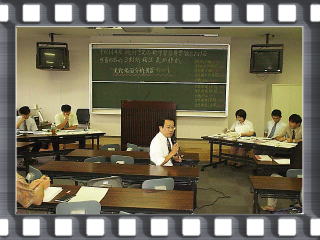 まさにディベートが始まります!
まさにディベートが始まります!
前回のディベートから多くを学んで、今回のディベートに活かせていたように思います。
今回は、ディベートのようすを写真に撮りました。前回は撮らなくてすみません。
ディベート後のディスカッションですが、論題について、今回は一方の側(否定側)に
有利な論題ではなかったか、という疑問がでました。
確かに一般的には、論題に関する否定的な見解が多く流布されており、その意味では、
肯定側に不利であったようにも思われます。
しかし、立論における戦略や、根底となる「哲学」の立て方によっては決して不利にばかり
なるとは限りません。
また、ジャッジにおいても、自分の意見が否定側であった場合、否定側であることは
変わらなかったとしても、少しでも肯定側に振れたならば、肯定側の勝利とする
必要があるのではないかという意見も出ました。
さらに、このような形での演習を継続していくことが望ましいという意見もありました。
論題に関しては、旧西ドイツにおける議論なども参考になるという意見、論題について
本質的に関わる部分と、派生的に関わる部分を区分して議論してはどうか、という
意見などが出ました。
みなさんからいただいた感想文を読む限りでは、今回の演習は、さまざまな点で実りの
多いものであったように思います。今後の研究に大いにいかしてくださるようお願いします。
記:2001年7月5日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
第1回目のディベートが行われました。みなさんお疲れさまでした。今回は、「公立義務
教育諸学校の選択の自由を認めるべきである」という論題で行いました。
初めに、ジャンケンで肯定側、否定側に分かれ、それぞれの立場から立論してもらいました。
ディベートの結果は、肯定側の勝利となりましたが、勝負の結果よりも、ここまでに至る
資料の収集、資料に従って論理的に筋道立てて立論すること、ディベートにおける質疑の
応酬といったこと自体に大きな意味があったように思います。
ぶっつけ本番のディベートにしては、とてもいいディベートだったのではないでしょうか。
ディベート後に、ディベートのやり方についてと、今回の論題についてのディスカッションを
行いました。
ディベートのやり方に関しては、
・相手の主張を崩し、自説の展開を有利にするような戦略に欠けているのではないか、
・作戦タイムの時間が短すぎて、相手の出方に合わせた展開を妨げていたのではないか、
・十分に準備していたことが、かえってフレキシブルな論の展開を妨げ、自説の主張に
偏る原因となっていたのではないか、
・ディベートに至る前に、ディベートのやり方自体の練習をしておく必要があるのではないか、
といった意見がでました。
論題をめぐっては、
・地域性という問題に関する目配りが不足していた、
・制度の問題と、現実の条件とを勘案した考察が必要だった、
・管理職の回転が早いことなど、インフラの問題を視野に入れる必要があった、
・現象面での議論にとどまらず、歴史や理論をふまえた議論に欠けていた、
・学校選択の実態調査や意識調査などのハードなデータが出されていない、
といった意見が出ました。これらの意見は、次回のディベートの参考にするにとどまらず、
研究活動にも生かすよう留意してください。
次回はもう一つの論題に関するディベートを行います。今回のディベートを参考に、準備に
力を入れてください。
記:2001年5月24日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
いよいよ、ディベートに向けての準備が始まります。ディベートの論題は、みなさんから出して
いただいた意見を参考に、次のように決定しました。
*****************************************************************************
①公立義務教育諸学校の選択の自由を認めるべきである。YesかNoか。
②平成14年度施行予定の新学習指導要領における学習内容の3割削減は是か非か。
*****************************************************************************
いずれの論題も、どう分析し、どこに焦点を当てて立論するのか、なかなか難しいところだと
思います。M2の方々のアドバイスを受けるとともに、スタッフへの質問なども積極的に
行ってください。
また、ディベートをいかに進めていくのかについて、ご紹介した参考文献はぜひ参照してください。
同時に、ディベートの審査を行うM2の方にも、やはり参考文献を参照していただきたく思います。
ディベートを行う目的については、次のようなお話をしました。
*****************************************************************************
ディベートとは、次の二つの点で単なる討論や議論とは異なる。
①資料やデータのリサーチをし、それらをもとに、さまざまな角度から問題を分析し、
賛否両論を視野に入れながら、論理的に議論を組み立てること。
②一方的に自説を主張するのではなく、相手側の議論の論点を的確につかみながら、論
理的に一貫性のある議論を組み立てること。
これらの点は、学術研究において求められる態度でもあり、これまで講義によって学習したことを
実習を通して身につけるために、ディベートが有益である。
また、ディベートの審査員には、次の二つの態度が要求される。
①双方の議論の要点を的確につかみ、その論理的な整合性や一貫性をとらえること。
②議論に内在的で、かつ、明確な基準と根拠をもって判定するとともに、建設的なコメ
ントやアドバイスを行うこと。
これらの点もまた、学術研究において求められる態度であり、これまで培ってきた成果をいかし、
さらに発展させるために、ディベートの審査員を行うことが有益である。
以上のことから、本演習においては、M1がディベートを、また、M2がディベート準備への
アドバイスとディベートの審査員を行うことにする。
******************************************************************************
現職の教員の方は、単に学術的研究のスキルを身につけるためだけではなく、現場に戻られてからも、
この経験が役に立つのではないかと思います。
記:2001年5月17日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
大前先生の講義はいかがだったでしょうか。図書館での実習も含めた講義で、文献探索の
スキルが身についたのではないでしょうか。
さて、来週以降は、これまで学んだことをいよいよ実際に活用するなかで、学問的研究の
トレーニングを行っていくことになります。
最終的なディベートに向けて、さまざまな資料を収集したり、賛否両論を視野に入れながら、
それらの資料を論理的に組み立てたりする作業を行います。
そのためにも、ディベートそのものについて勉強することが必要です。以前に紹介した文献以外に、
新しく出た本があります。これはなかなかいいのではないかと思われますので、紹介します。
茂木秀昭『ザ・ディベート -自己責任時代の志向・表現技術』ちくま新書(292)、2001年。
こういった本も必ずお読みになって、実習に入るようにしてください。
記:2001年5月11日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
昨日はおつかれさまでした。
調査の話に先立って、学問的研究の手続きについてちょっとお話ししましたが、参考になったでしょうか。
次回は、文献収集の方法について大前先生から具体的なお話があると思います。
その後は、みなさん自身がディベートに向かって、実際に資料や文献を収集し、それらのデータを
論理的に構成するという作業を行っていきます。
その作業の過程で、疑問点や相談の必要性なども出てくると思います。そういったときには、
遠慮せずに、いずれのスタッフでも結構ですから、尋ねていってください。
記:2001年5月8日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
今年度の実践場面分析はリニューアルして、研究の世界への橋渡しの役割を
より強く担うことになりました。
4月26日には、古賀先生より学問的研究とはどのようなものかについてお話がありました。
5月10日には、調査とはどのようなものかについて藤田が話をします。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇