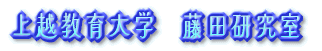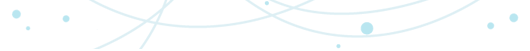|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
記:2004年7月9日
今回は、「学校給食は、廃止すべきである」という論題でディベートを行いました。子ども、親、教師のいずれの立場にとっても切実な問題だと言えるでしょう。
議論も白熱し、とてもおもしろいディベートになっていたように思われます。ディベートのやり方についても、回数を重ねるごとに洗練されてきているようです。
学校給食の問題は、人権の問題、学習内容や方法の問題、さらには、幼児教育コースの丸山先生がご指摘くださったように、経済問題や国の政策に至るまで、さまざまなことがらと関係していることが分かりました。小さい窓から、大きな景色が見えるということの典型例を見るようでした。
さて、反省会では、今回も「かみあう議論」についての意見が出ました。荻原先生が指摘くださったように、すでに議論のなかには、かみあう論点がたくさん出されていたと思います。それらをかみ合っているものとして提示することが大切だということでしょうか。
前回お話ししたように、抽象度を上げて土俵を設定し、そこに双方の議論を位置づけて論じることができると、聞いている側も議論がかみ合っているなと感じることになるでしょう。
そこで、今回のディベートを例に、どのような「かみ合わせ方」が可能か考えてみることにしましょう。ただし、今回のディベートの内容そのままではなく、大幅に改変してありますことをご承知おきください。
まずは、肯定側の立場からの反駁の例です。
<土俵の設定>
それぞれの主張の拠って立つところについて比較してみましょう。
<Desctiption(描写)>
否定側は、法律で定められていることと、多くの学校で実施されていることを学校給食を存続すべき理由として挙げています。
<Interpritation(解釈)>
法律は社会の変化とともに改正されていきます。また、多くの学校で行われていることも変化します。たとえば、国連で採択された女子差別撤廃条約を日本が批准したことによって、日本の国籍法が改正され、子どもの国籍は父親の国籍となるとされていたものが、父親と母親のどちらかの国籍となることもできるようになりました。法律に定められていることをそのまま存続させればいいわけではないことが分かります。また、以前は多くの学校で女子児童は体育着としてブルマーをはかせられていましたが、時代の変化とともに現在ではほとんどなくなっています。
<Evaluation(評価)>
つまり、否定側の主張は、時代や社会の変化とともに変わってしまうあやふやなものの上に立脚していると言えるのです。
<Desctiption(描写)>
それに対し、私たち肯定側は、学校給食を廃止すべき理由として、食物アレルギーを抱える子どもに対する危険の除去を挙げました。
<Interpritation(解釈)>
これは、弱者や少数派の利益こそ優先して守るべきであるという考えに基づいています。その考え方は、時代や社会が変わったとしても、常に有効だといえるのではないでしょうか。
<Evaluation(評価)>
つまり、私たちの主張は、どの社会、いつの時代でも尊重すべき原理の上に立脚しているのです。時代や社会とともに変わってしまう不確かなものに立脚する否定側よりも、私たちの主張のほうが妥当性が高いことは明らかです。
では、否定側の立場の反駁の例としてはどのようなものが考えられるでしょうか。
<土俵の設定>
それぞれの立場において、学校給食の廃止や存続の効果についてどう主張されているか比較してみます。
<Desctiption(描写)>
肯定側は、学校給食を廃止すれば、それぞれの生徒が別々の食事をとることになるため、学校給食の画一性が打破され、個性豊かな食育が可能になると主張しています。それに対し、私たち否定側は、学校給食を通してこそ食育が可能になると主張しています。つまり、どちらの立場も、食育が可能になることを効果として主張しているのです。
<Interpritation(解釈)>
ここで、考えなければならないことは、どのようなプロセスによってその効果が実現されるかということです。肯定側は、学校給食を廃止することが、どのように個性豊かな食育に結びつくのか、具体的な経緯を主張していません。しかし私たちは、教科書や資料集といった共通の教材を通して学習する教科の学習と同じように、給食を共通の教材として活用することや、メニューはどのようなことを勘案して作られているのか、食材はどのようなプロセスで料理されるのか、食材はそもそもどこから来るのか、といったさまざまな学習課題について指摘しており、食育という効果がどのようにもたらされるのかについて、具体的な過程を説明しています。
<Evaluation(評価)>
つまり、肯定側の主張は非常に抽象的であり、効果がどのように達成されるのか不明です。それに対し、私たちは、食育という効果がどのように現れるのかを具体的なプロセスを含めて主張しています。よって、私たち否定側の主張する効果のほうが明らかに現実的であると言えるのです。
このような反駁をいくつかの点について行うことによって、「かみあった議論」を作っていくことができます。その場合、立論の議論について反駁するだけでなく、第一反駁で相手側が行った「土俵の設定」自体を第二反駁で反駁するということもありえるでしょう。
反省会でお話ししたように、上記以外にもさまざまな土俵が設定できると思います。たとえば、「深刻性」や「重要性」のように、どんな論題でも使えそうなものもありますし、その論題だからこそ設定できる土俵もあるでしょう。
ここで説明していることは、さまざまに主張される発言にはそれぞれどのような意味があるのか、どんな文脈を設定すると共通項が見出されるのか、といったことをメタに考える作業(分析的に考える作業)です。
その作業を、ディベートをしているまさにその場で行うのは大変なことでしょう。しかし、その作業は、前にも言いましたが、学校の教室の中で教師が常に行っていることなのではないでしょうか。教師は、たくさんの児童生徒のさまざまな発言を瞬時に把握し、位置づけながら、学習を組み立てているはずです。授業中などになされた意味の分からない発言は、その発言をした児童生徒の問題ではなく、その意味を位置づけることのできない教師の問題であるかもしれません。
では、いよいよ次回はディベートも最終回となります。監視カメラがどう議論されるのか、とても楽しみです。
記:2004年7月6日
今回は、「教員免許は、更新制にすべきである」という論題のディベートを行いました。免許の更新制とはどのようなもので、誰にとってどのような利点や弊害がありうるのか、教師のみならず教育に関わる人々の多くが関心を抱くことがらではないでしょうか。
どちらのチームも骨太の論理を立てて、なかなか秀逸な議論になっていました。ディベート後の話し合いでは、論点を列挙するのではなく、構造化する方が分かりやすいのではないか、議論をかみ合わせるのはなかなか難しいといった意見が出ていました。
実は、それら二つの指摘は密接に関わっているように思われます。そこで、論点を構造化するとか、分析的に考えるとかいったことについて考えてみましょう。
複数の論点を提出する場合、ディベートなら論題を肯定すべき具体的な理由を複数提出する場合などですが、それらの論点を単に列挙するのではなく、論点同士にはどのような関わりがあるのかについて、抽象度を一段上げて考えることが論点の構造化であり、分析的に考えるということです。
たとえば、新しい制度というテーマについて複数の論点を提示する場合、それらは制度の「理念」に関わるものなのか、制度を導入する「手段」に関わるものなのか、制度がもたらす「効果」に関するものなのかといった具合に考えるということです。
そうすることで、自分たちの提出する論点は、テーマのどういった点に言及しているのか、論点は相互にどう関係しているのかについて理解できます。論点の構造化は、テーマ側に目を移せば、テーマの構造を考えることでもあります。なぜなら、自分が取り組んでいるテーマがどのような論点からなるものなのかを分析していることでもあるからです。
論点が構造化されていれば、それぞれの論点を意味づけながら主張することができます。単に論点を列挙するよりも、ジャッジが論点の意味を理解しやすくなると言えるでしょう。
また、論点の構造化(=分析的な思考)は、かみ合った議論にも有益です。
双方の主張している個々の具体的な論点はそもそもかみ合いません。それぞれが独自の立場から違ったことを主張しているのですから。しかし、それらをかみ合わせるためには、相手の主張がどのような点に言及しているものなのかを位置づける必要があります。つまり、相手の具体的な論点の意味を分析的に考え、上記の例であれば、「理念」や「手段」、「効果」などに位置づけるということです。そのように抽象度を一段上げたところに共通の土俵を設定し、その土俵上で話をすることで、かみ合う議論をディベーター自ら「作り上げていく」わけです。その意味において、議論をかみ合わせられるかどうかもディベーターの力量の一つだと言えるでしょう。
もちろん、相手側の論点をこちらなりの解釈で「位置づける」のですから、相手がその位置づけ方に納得するとは限りません。また、相手もこちらの論点を相手なりの仕方で「位置づける」でしょう。
相手を言い負かしたり、納得させたりするのではなく、「ジャッジ」を納得させるのがディベートの目的です。ジャッジが説得力があると思うような位置づけ方をし、それに則って一貫したかみ合う議論を構築できるかどうかが勝負の分かれ目です。
では、次回の論題は「「学校給食は、廃止すべきである」となります。また、最終回は「不審者侵入防止のため、校門に監視カメラを設置すべきである」という論題です。
これまでにも増して白熱した議論が展開されることを期待しています。
 |
記:2004年6月29日
これまで学習してきたことを実習を通して身につけるため、いよいよディベート大会が始まりました。
今回は、「小学校に、英語教育を導入すべきである」という論題で、小学校の教師にとっては特に切実でホットなものでした。ちなみに、次回は「教員免許は、更新制にすべきである」、さらにその次は「学校給食は、廃止すべきである」という論題となっています。
準備もきちんと行われていたようで、なかなかいいディベートになったように思います。ただ、複数のジャッジの方々から、言葉の定義を初めにしておくと、もっと議論がかみ合うのではないかというアドバイスをいただきました。次のディベーターのみなさんは心にとめておいてください。
ディベート後の話し合いで、反駁は原稿を前もって準備することができないので、議論の材料をその場で主張として組み立てていかなければならないが、なかなかそれがうまくいかなかった、という反省点が出されました。
基本的には、以前に学んだ議論の組み立て方をを応用してください。つまり、どんな主張をしたいのか、それはどんな根拠に基づくのかを順序よく述べるということです。
しかし、とっさにそんなことができれば悩みはありません。そこで次の三つのことを試してみるのも役に立つかもしれません。
一つめは、話し始める前に、話す材料を構造化しておくということです。たとえば、五つの材料があった場合、それは五つとも並列的に並び立つものなのか、それとも、大別すると三つに分けられて、残りの二つは、三つのうちのひとつを補強するものとして位置づけられるのか、厳密でなくてもいいですから、大まかに材料を組み立てる方向で考えてみるということです。
二つめは、話し始めるときにナンバリングすることです。たとえば、「ここでは三つの点について、肯定側の立論に反駁します」という具合に、話すことを初めに限定するというやり方です。これには、話が拡散してしまったり、何をいま話しているのか分からなくなってしまったりするのを防ぐ効果があります(もちろん100%ではありませんが)。
三つめは、DIEメソッドと呼ばれる方法です。
相手に自分の主張を伝えるためには、まず何について話をしようとするのかを説明しなければなりません。それが「Description(描写)」です。話そうとする点について自分は分かっていても、相手が分かっていなければ、結局のところ話は通じません。今回のディベートでも、どの論点のどんな部分について話をしようとしているのか、きちんと説明しないままに話を先へと進めてしまうケースも見られました。
次に、話題としたい点の描写がすんだら、それをどのようなものとして考えるのか、「Interpritation(解釈)」を述べていきます。ここは、根拠や論拠に該当する部分と言えるでしょう。
そして最後に、ここまで述べてきた解釈をもとに、「Evaluation(評価)」をします。つまり、「だから、否定側の反論は的を射ていません」とか、「肯定側の主張のほうが妥当性が高いと言えます」とかいう判断を述べるのです。
IとEの部分は前後が入れかわってもいいと思いますが、それぞれの部分を、ゆっくりと説明していくことで、ジャッジにも分かりやすいスピーチになるでしょう。もちろん論点が二つあれば、DIEメソッドも二回用いることになります。いずれにせよ、この三つの部分をきちんと言おうと意識すること、三つのうちの何をいま話しているのかをチェックすることなどが役に立つかもしれません。
さて、ディベートの反省会に、ディベートをした人以外の参加者が少なかったことがとても残念でした。もちろん正規の授業時間外ですので、無理に参加する必要はありません。しかし、議論をすること自体について、また、論題の内容について、ジャッジをした人やディベートを聞いていた人からさまざまな意見をもらうことによって学びを豊かにしたいと考えていますので、都合の許す方はぜひともご参加ください。
 |
記:2004年6月16日
今回は、「ディベートのジャッジ」についてお話ししました。
そもそもディベートの目的は、ジャッジを説得することです。ですから、ジャッジに要求されるのは、一にも二にもディベーターの言うことをきちんと聞いて、理解することですし、ディベーターには、ジャッジがきちんと理解してくれるように話すことが求められます。いずれも、教師にとって、まさに教室で必要とされる力量だと言えるでしょう。
ジャッジは、印象だけで判断するのではありません。ディベーターたちが話したことをフローシートと呼ばれる用紙に記録し、それをもとに判断します。また判断に際しては、論題に対する個人的意見にとらわれず、ディベートで話された内容だけで判断をすることが求められます。記録した内容ををもとに、この講義特製の「判定用紙」にある規準に従って勝ち負けの判定を行います。
話を聞いて記録すると言うのは簡単ですが、実際にやってみるとかなりたいへんな作業です。そこで今回は、話の要点を聞き取って記録するエクササイズを行いました。「行列のできる法律相談所」の弁護士たちの主張をビデオから聞き取り、記録してみました。班ごとに記録の内容や仕方について議論をした後、それを踏まえて、実際のディベートをビデオで見ながら記録し、判定を行うという実習を行いました。
ジャッジを行う方にとっても、ディベートを行う方にとっても、ジャッジの仕方を身をもって体験したことは、とても役に立つのではないでしょうか。
さて、これまでに学習してきたことを実践を通して身につけるため、いよいよ6月24日から4週にわたってディベート大会が開催されます。第1回目は、「小学校に英語教育を導入すべきである」という論題となります。第1回目に当たったチームの方は、頑張って準備をしてください。
では、ディベート大会をお楽しみに。
記:2004年5月28日
今回は、「ディベートの方法」というテーマで、立論の構成、ディベートの仕組み、リサーチの方法という3つの点についてお話ししました。
まず、前回の講義に出てきた「主張←根拠(証拠・論拠)」という議論の構造が、立論にはどう関係しているのかを、殺人事件の捜査を題材に考えました。「犯人はこの人だ!」という「主張」は、ひとつの根拠だけに支えられているのではなく、複数の根拠によって支えられています。また、それらの根拠も、細かく見ると「主張←根拠」という構造を持っています。つまり、大きな「主張←根拠」は、たくさんの小さな「主張←根拠」によって構成されているわけです。立論を考えるときにも、立論に対して反論するときにも、このような立論の仕組みをきちんと理解することが必要です。
次に、ディベートの仕組みについて説明しました。概略をお話ししただけですので、詳細については講義の中で示した参考文献をよく読んでおいてください。なお、今回の講義で説明した用語と、参考文献で用いられている用語は必ずしも一致していません。重要なのは次の2点です。参考文献では「メリット・デメリット」という言葉が多用されていますが、今回の講義では、論題を肯定・否定する「根拠」として説明しています。また、『ザ・ディベート』という本で「哲学」として説明されていることは、今回の講義では「根本的論拠」として説明しています。その他に分からないことがありましたら、ぜひご質問ください。
この講義では、ディベートについて、試合当日に行われるものだけではなく、論題に関するリサーチや各グループ内での話し合いなどのプロセスをも含めてとらえています。そこで最後に、リサーチの方法についてエクササイズを通して学習しました。今回は特に、多角的に考えるとは具体的にどうすることかについて考えました。6つの方法を紹介しましたが、それらを柔軟に駆使して実りの多いリサーチをしてくださることを期待しています。
6月3日は学部生が教育実習のために不在なので、次回の演習は6月10日です。ディベートのジャッジについて学習します。
記:2004年5月22日
前回に続いて荻原先生にご担当いただき、「議論をどう組み立てるか」というテーマについてさらに深く考えました。
まずは、前回の復習をしました。特に、「根拠もどき」に気をつけることと、反論は「解決策」を述べることではないという点が重要でした。
ある意見に賛成するか反対するかという判断は人によって分かれます。つまり、意見とは「議論の余地が大きい」ものであるわけです。そこで、その意見を支持する根拠をつけることで、聴衆を説得することになります。ですから、根拠になりうるものは、できるだけ議論の余地の小さいものにする必要があります。なぜなら、根拠として「(議論の余地の大きい)別の意見」を挙げたとしても、議論の余地がさらに拡大するだけで、さらに説得できなくなってしまうからです。そのような根拠のことを、荻原先生は「根拠もどき」と呼んでいました。
また、生じている問題について議論をしているのに、その問題を生じさせなければいいという解決策で反論をすることは、議論を別なものへすり替えていることになります。生じている問題についての議論ではないわけですから。解決策によって反論するというやりかたは、同じ土俵に立った議論とならないということに気をつけてください。
今回は、ある文章の主張や根拠をみんなで考えるというエクササイズを行いました。なかなか難しい作業で、必ずしもすっきりとした回答は得られなかったのは残念です。しかし、回答を得られたかどうかよりも、作業すること自体に意味があったように思います。というのは、相手の主張や根拠を同定するという作業自体が難しいということが自覚できたからです。
今回の作業は、相手の議論がどのように組み立てられているのかを考える作業でした。木にたとえると、根っこが「論拠」、幹が「証拠」、葉や花である「主張」はそれらに支えられていると考えることができるでしょう。相手の主張を乗り越えるためには、主張の根や幹をきちんと同定し、そこを切り崩さなければなりません。普段はそこまでやりませんし、やったとしても相手の主張や根拠を同定すること自体が容易ではありませんから、しばしば堂々巡りの議論になってしまったり、水掛け論になってしまったりするのです。それらのことをしっかりと認識しておかなければ、未然に防ぐことはできません。
次回は、これまでの学習をディベートという形で実習する第一歩として、ディベートに関して学ぶことになります。お楽しみに。
記:2004年5月15日
今回は、荻原先生にご担当いただき、「議論をどう組み立てるか」というテーマで、主に主張と根拠について学習しました。
議論とは、単に意見を述べ合うことなのではなく、根拠をもって反論し合うことなのです。根拠のある反論であることによってこそ、「かみ合う議論」ができるのでしょう。
エクササイズとして、ある主張の根拠を考えてみる実習をしました。まずは一人だけで根拠を考えてみましたが、それをグループの他の人と合わせてみたとき、自分にはない発想に触れて少なからず驚いたのではないでしょうか。そういう場合にはぜひ、自分の発想がどう限定されてしまっているか、一歩離れたところから自分自身を観察してみてください。
次に、自分たちで考えた根拠に対する反論を考えるというエクササイズをしました。普段の場面では、自分の考えに対する反論まで自分で考えることはめったにありませんから、なかなか難しい作業だったように思われます。その作業を通して、主張の根拠といってもさまざまであるということが分かりました。つまり、すぐに否定されてしまう弱い根拠もあれば、水掛け論に陥ってしまうような根拠もあり、なかなか反論するのが難しい根拠もあるということです。しかし、普段はそこまで考えず、気軽に主張してしまっているのではないでしょうか。
最後に、根拠(reason)は、証拠(evidence)と論拠(warrant)の2つに分けられるということが説明されました。ある証拠がどうして根拠となりうるのかを説明するものが論拠です。
きちんとした議論を組み立てることは思ったよりも難しいということが実感できたのではないでしょうか。
さて、次回までの宿題が出ています。配布されたプリント3枚目の例文4を読んで、設問のこたえを考えてきてください。設問は、例文4の主張は何か、その主張を支えている論拠は何か、その論拠にはどう反論できるかというものです。また、プリント4枚目もきちんと読んできてください。
次回は今回のつづきとなります。お楽しみに。
記:2004年5月6日
3回目の今回は、大前先生のご担当で、教育情報訓練室で実際にパソコンを操作しながら、文献や書籍の検索について学習しました。
パソコンを利用すると、書籍の検索だけではなく、学会誌や紀要などに掲載された論文を検索することもできることが分かりました。その場合、どのようなキーワードによって検索するかが重要です。自分一人だけではなかなかアイディアがたくさん出てこないものですから、他の人との対話などを通して、さまざまなキーワードを見つけ出すことも大切です。
大前先生も講義の中でおっしゃっていましたが、コンピュータによる検索だけではなく、実際に体を動かして検索してみることも必要です。自分の設定したキーワードでは引っかかってこない文献に出くわすこともありますし、学会誌のバックナンバーをすべて調べてみることで、興味や関心が広がっていくこともあるでしょう。また、教科の学習や進路指導、特別活動など、さまざまなテーマ別に論文をまとめた冊子もあります(たとえば、国立教育研究所編の『教育研究論文索引
』 )ので、関心のあるテーマの部分を網羅的に調べてみるために役立つでしょう。
今回学習したスキルを有効に生かし、みなさん自身の研究を進めていくためにも、自分自身の研究に関係しそうな文献を実際に探して入手し、読んでいってください。学会誌や紀要、雑誌などの論文の場合は、後で必要になったときのことを考え、きちんとコピーを残しておきましょう(いつ必要になるか分かりません)。また、できれば、どんな論文を読んだのか、それはどんな内容だったのか、どんな印象の論文だったのかといったことについて、読書ノートやカードをつけておくと役に立ちます(どんどん忘れてしまいます)。
世の中には本当にさまざまな文献や資料があります。今こそ、それらをじっくりと探したり、読んでみたりするときではないでしょうか。
では、また次回。
記:2004年4月23日
第2回目の演習はいかがでしたか? 今回は、安藤先生のご担当で、整理と分析について実習を含めて学習しました。
実際に行ったのは、日本におけるさまざまな教育問題を整理・分析するという作業でした。グループごとに、現代の日本で教育問題とされている問題をたくさん考え、それらを整理・分析したのです。
最初にやった作業では、多くのグループが「整理」にとどまっていたように思います。というのも、整理してはみたけれど、「だから何?」という状態だったからです。言い換えれば、諸問題を整理したことによって、新しい何かが見えてきたわけではなかったということです。
2回目にやった作業は、最初とは異なり、諸問題全体を見渡しながら整理するというものでした。その結果、整理することによって、教育の諸問題を構成する要素同士の関係について見取り図を描くことができたり、諸問題の広がりがどのような構造を持っているのかを説明できたりしていたように思います。つまり、単なる整理にとどまっていたのではなく、整理することによって教育の諸問題の新しい見え方を提出する「分析」になっていたということです。
「原因の所在」という観点から整理することによって、教育の諸問題は3つの原因から構成されているという分析を提出したグループもありました。また他のグループは、「問題が生起するところ」という観点から諸問題を整理し、個人、個人と個人を取り巻く人間の間、個人と広い社会との間という3つの場所で問題が生起すると分析していました。
このように、「ある観点」から問題を整理することによって、その問題に関する「新しい見え方」を提示することが「分析」なのです。
私たちの抱えている問題の新しい見え方を提示し、それまで見えてこなかった解決の方向性をも示唆するような、するどい分析をしたいものですね。
では、また次回をお楽しみに。
記:2004年4月22日
いよいよ実践場面分析演習が始まりました。
教育実践の中で直面せざるを得ない諸問題について、どのように分析し、判断し、実行していったらいいのか。それらの問題に関する考えを、同僚や保護者、さらには地域社会の人々にどう説明していったらいいのか。
どこかにある答えを探し出そうという「受動的思考=知識受容」という態度ではなく、自分自身で答えを創り出していくという「能動的思考=知識創造」という態度へ転換していくため、さまざまな実習を通して学んでいきます。
今回は、考えるエクササイズをいくつか行いました。自分の思考には一定のバイアスがかかってしまっていること、そこを抜け出して別の見方をしてみることの難しさを実感することができたのではないでしょうか。
学部の実践セミナーと合同で行われるため、世代も立場も異なる人々の協働作業を行っていくことになります。そういう状況におけるコミュニケーションスキルをも向上させていけるよう期待しております。
みなさんにとって実りの多い演習となるよう頑張っていきましょう。
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Copyright(c)2004 FUJITA Takeshi. All Rights Reserved. |
|

|
|
 |