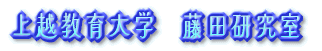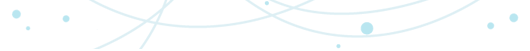|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
記:2004年7月14日
今回は、子どもをとらえなおすという作業をしました。
学校の教室にはさまざまな子どもたちが、それぞれの事情を背負ってやってきています。ですが、日本の学校文化では、どの子にも同じように接するという対応をとることが多いように思われます。もちろんそのやり方が功を奏する場合も多いのでしょう。
しかし、今回見たビデオのように、子どもをしっかりと保護したり、しつけたり、教育したりできない「弱い家庭」が少なからず存在しています。そういった境遇におかれた子どもたちを、そうではない子どもたちと同じように扱うことで、他の子どもたちとの格差をますます広げてしまう可能性もあるのです。
教室には、みなさん自身の家庭的・文化的背景とはかなり異なる多様な背景をもった子どもたちが存在しているのであり、それぞれの子どもの抱えている課題も多様です。その多様性に対しどう対処していくかは、教師の切実な課題なのです。
さて今回は、レポートの課題も出題しました。ココをクリックするとレポート課題がPDFファイルで見られます。提出期限は、2004年9月7日(火)です。研究室のドアに封筒をはっておきますので、そのなかに入れてください。
また、9月7日の4限には、本学の講義棟102教室で、日本の小学校現場で長年フレネ教育を実践してきた先生の講演があるようですので、ぜひ聞きにいってください。
では、今回のみなさんのリアクションペーパーをいくつか紹介します。
・今日ビデオで見たような、いわゆる「家庭に事情がある」子を今まで自分は考慮せずにいたことに気づいた。
→自分が教壇に立ったときに出会うと想定していた子どもたちには、実は偏りがあったということですね。私たちは、自分自身の育ってきた環境が「普通」であると考えがちです。それは、自分自身の経験してきた学校のあり方が「普通」であると考えてしまうのと同じです。この講義では一貫して、それらの「普通」をとらえなおし、私たちの「普通」が作られたものであること、他の「普通」もあること、「普通」が私たちの見方・考え方を狭めてしまっていることなどを学んできたわけです。「普通」からのとらわれから自分自身を解放することが、柔軟な思考や新しいものの創造につながっていくのではないでしょうか。
・世の中には、ビデオで見たような境遇の人たちがいるということは頭では理解していたし、援助できることがあって、その機会があれば、援助したいと漠然と思っていた。しかし実際、将来の私たちに身近に迫る可能性のある問題だということを知り、これまで考えていたことが漠然としていただけに、教師として何ができるのかという問いに答えが出せなかった。
→貧困に苦しむ人々や、病気に苦しむ家族などは、どこか遠い世界のことだったのかもしれません。しかし、教師とはまさに、そういった現実のなかに生きる子どもたちと向き合う仕事なのです。そのことを実感していただけたようで何よりです。教師として何ができるのかという問いは、すぐさま答えの出るような問いではありません。しかし、子どもたちは目の前にいるのですから、問い続けなければならない問いですし、最善とは限らずとも実践的に答えを出していかなければならない問いなのです。
・私たちは、どんなに整った環境のなかで育ってきたかを実感しました。しかし、ビデオに出てきた子どもたちは、みんな精一杯生きていて、不幸であると決めつけることは間違いであるように思いました。
→その通りですね。もしあなたよりも経済的に豊かだったり、社会的地位が高かったりする人たちが、あなたのことを「不幸な境遇にいるね」と言ったとしても、あなたは納得しないでしょう。幸せか、不幸かというのは、何か一つのものさしで客観的に測れるものではないのかもしれません。
では、よい夏休みを!
記:2004年7月9日
今回は、前回に引き続き、これまでビデオで見てきた進歩主義的な学校の特徴についてまとめました。
2つのチームに分かれ、特徴として気づいたことをカード化し、それらを分類していきました。個々のまとまり同士がどのように関係しているのか、全体的な特徴にも目配りして、模造紙にまとめました。
院生さんが何人かオーディエンスとして来てくださいました。その方たちに、これまで学んだことについて発表しました。2つのチームそれぞれが作った模造紙は次のものです。クリックすると大きくなります。
いずれのチームも、学びの主体が子ども自身であることを中心に構成しています。一方のチームは、教師・保護者・学習環境という三者が子どもたちを取り巻いている構図を描いています。もう一つのチームのものは、やや未整理な状態なのは残念ですが、支援者・学習空間・学習内容・学習形態といった要因が子どもたちを支えていると考えることができそうです。
どのようなことを学んだかを整理することも課題ですが、学んだことをどのように生かしていくかが本当の課題です。頑張っていきましょう。
では、次回は夏休み前最後の講義となります。いつもの教室で行います。暑くて大変ですが、あと一回ですから何とか乗り切りましょう。
記:2004年6月30日
今回は、これまでビデオで見てきたフレネ学校、レッジョ・エミリア市の幼年学校、伊那小学校といった、いわば進歩主義的な学校には、日本の一般の学校に比べた場合、どのような特徴があるのかを考えました。ビデオを見っぱなしにするのではなく、きちんと振り返りをしておこうというわけです。
まずは、ブレーンストーミングをしました。ビデオを見て気づいたことを、考えつく限りカード化しました。続いて、4、5人でグループを作り、カードを出し合って、それらのカードを分類していきました。分類したカードの束には「表札」をつけ、他の束との関係も考えました。
今回は、上記の作業までしかできませんでした。つづきは次回おこないます。進歩主義的な学校には全体としてどのような特徴があるのか、それはどういった部分から成り立っているのかなどについて、模造紙に描き出していきます。
今回と同じように、人文棟7Fの会議室でおこないますので、お間違えのないようにお願いします。
記:2004年6月28日
今回は、これまで見てきたフレネ学校やレッジョ・エミリア市の幼年学校のように、子どもの主体的な学習を支援している日本の学校のビデオを見ました。
ビデオで見た学校は一般の公立小学校でしたが、総合学習(現在の「総合的な学習の時間」とは異なります)を軸にして、子どもたちの学習を組み立てていました。
算数や理科などの学習が、子どもにとって必然性のあるものとして、だからこそ、主体的に取り組むものとして成立していました。
フレネ学校のビデオを見た時、フレネ学校は外国だからできるのであって、日本では無理だという意見がありました。しかし、日本の普通の公立学校でも、子どもの主体的な学習を支援するような教育は、十分にできるのです。
しかも、今回見たような学校は、実は、古くから日本の各地に存在しています。今後それらにも学ぶことで、自分の受けてきた教育の枠(自分の中にある学校文化)を自ら越え、新しい教育や学校を作り出す担い手となってくださることを期待しています。
では、今回のリアクションペーパーを少し紹介します。
・今回のビデオを見て、日本にもあのような学校があることに驚きました。そして楽しみになりました。私も先生になれたら、あんな学級を作りたいと思っていました。先生も大変な努力をして子どもたちをサポートしていたと思います。どんなサポートをしていたのかを知りたいと思いました。
→これをきっかけにして、豊かな学びを生み出すさまざまな方法について学んでいきましょう。日本で現在おこなわれているものはもちろん、これまでにどのような実践が、どのような考え方に基づいておこなわれてきたのかについても勉強してみてください。それらはきっと、あなた自身の教育実践にも生かされるはずです。
・あの小学校出身の人が教師になったら、きっといい授業ができるのではないかと思います。小学校のときに、あんなおもしろそうで、いきいきとした授業を受けているわけですから、自分が授業する立場になったときにも、イメージがふくらみやすいのではないでしょうか。
→そうかもしれません。しかし、それは必要条件ではないでしょう。ビデオに出てきた先生だって、自分自身があのような授業を受けて育ったわけではないでしょうから。ですから、みなさんにも十分に可能だと思うのです。
・牛のフンを集めて肥料にして畑にまき、できたトウモロコシを売り、売ったお金で牛のえさを買い…。これぞ「創造学習」だと思いました。何をしようと思って「総合学習」をはじめようとしたのか、という本質をもう一度見直さなければいけないのではないかと思いました。
→おっしゃるとおり、今の学校で行われている「総合的な学習の時間」はいったい何をしようとしているのか、きちんと考える必要がありますね。そのためにも、これまでビデオで見てきたようなさまざまな学習のありかたや本質について、まだまだたくさん勉強する必要がありそうです。
では、また!
記:2004年6月22日
今回は、小学校よりも前の学校段階においてユニークな教育実践を行っているところのビデオを見て、学校の文化についてさらに考えを深めていきました。取り上げたのは、イタリアのレッジョ・エミリア市の幼年学校です。
レッジョ・エミリア市の幼年学校は、これまで見てきたフレネなどの進歩主義的な教育の影響を受けながら、独自な教育を行っていました。
光にも気を配った学校建築、表現を中心とした教育方法、子どもの学びの軌跡を綿密に記録していくドキュメンテーション、ドキュメンテーションをもとに話し合いながら創り出していくカリキュラムなど、学校の役割や教師の役割が私たちの「当たり前」とはずいぶんと異なっていました。
また、親たちが積極的に教育に参加しているようすも、日本の親たちの関わり方と大きく違っていました。
このようなレッジョ・エミリア市の教育は、自由に表現できる個人をつくりだしていくことは共同体のためにもなるのであるという考え方、教育とは注入することではなく、自分の中にあるものを表現できるようにすることだという考え方に基づいていました。
みなさんが将来、学校を改革し、新しい学校を創造していくためには、みなさんの思考や想像力がこれまでの枠組から解放されていることが必要です。解放するためには、さまざまな学校文化のありようを知ることによって、自分たちの学校文化をとらえ直す作業が有益なのです。
では、今回のリアクションペーパーを紹介しましょう。
・表現することは難しいと思っていたのは自分のせいではなく、これまでの環境のせいだったのだと思った。
→レッジョ・エミリア市の幼年学校のように、表現するための多様な手段が準備されているなかで、さまざまなものを表現するように働きかけられるような環境の中で小さなころから育っていれば、シャイで表現下手の日本人は育たないのでしょう。あなたのように「自分のせいだ」と思いこむ人間を増やさないようにするにはどうしたらいいか考える必要がありそうです。
・中学校で、いくつかのテーマからイメージするものを表現させる活動をしたが、なかなか表現できなくて時間がかかっていた。小さいころから表現活動をする機会が少ない日本では、いきなり表現させようとしても難しいと感じた。
→表現するのも練習の積み重ねが必要なんですね。しかし、レッジョ・エミリア市の幼年学校の子どもたちは、なにも表現の練習をしようとしているわけではなく、学校のさまざまな活動を楽しくしていたら結果として練習になっているのですし、だからこそしっかりと身についていくのかもしれません。
・子どもは何も知らないから教えてやらなければならないという考えがあったのですが、「何もできない、知らない」と決めつけていくと、かえって彼らはその通りになってしまう気がしました。ビデオの中に出てきた「教育は押し込むのではなく引き出す」という言葉は、ぜひ実践していきたいことだと思います。
→表現するものをすでに持っている人間としてみなすからこそ、レッジョ・エミリア市の幼年学校ではあのような教育方法を用いているということですね。子ども扱いすることは、いつまでも子どもを子どものままに押しとどめることでもあるのでしょう。子どもという存在をどうのようなものとして考えるかが、日本とは大きく違っているようです。
では、また次回!
 |
記:2004年6月14日
今回も引き続き、フレネ学校のビデオを見ながら、学校の文化について考えました。
フレネ学校では、子どもたちも学校の運営に参加する姿が見られました。子どもたちは学校協同組合のメンバーとして、自分たちの文集の紙を買うお金や遠足に出かける費用などを、バザーを開いたりして自ら調達していました。たとえば、授業の中で行うケーキ作りも、「ケーキ作りのためのケーキ作り」ではなく、それらを売って学校協同組合の運営資金を獲得する目的のために行われていました。
また、学校のためになることを自由意志で行う「イニシアチブ」が行われていました。全校集会では、自分たちの身のまわりで起きた問題について自由に発言し、問題をみんなで共有していました。
日本の学校を「当たり前」だと思っている私たちには、フレネ学校で起きていることを理解するのは難しく、まるで嘘か作りごとのように見えてしまいます。そのことは、私たちが意識しないままにかけている「めがね」の力がとても強力であることを示しているのでしょう。
では、今回のリアクションペーパーからいくつか紹介します。
・フレネ学校の子どもたちの発言を聞くと、大人がなるほどと思えるような意見をすんなりと言っていることに気づき、驚きました。実習先では4年生の教室に入ったのですが、話すことすべてがかわいらしいと思えるものでした。しかし、フレネの子どもはしっかりとした発言で、同じ年でもこうも違うものかと思いました。
→日本では、いつまでも子どもを子ども扱いするので、なかなか成長できないのかもしれません。フレネ学校の生徒たちを見ていると、大人になるためには、大人扱いすることが必要であることに気づかされます。
・フレネ学校では、学校で学ぶことがらが子どもたちの生活に近いということを感じました。自分たちの生活に直接関係することを学ぶことで、積極的に、自ら進んで学ぶことができるのだと思いました。授業や規則を子どもたち自身で作っているからこそ、自由のうらに責任を感じながら行動しているように思いました。
→しなければならないから仕方なく学習するということでもなく、勉強のための勉強ということでもなく、学習していることが自分の生活にどのような意味があるのかを理解しながら学べることは幸せですよね。そうであれば、学習することも楽しいでしょうし、よく身につくことにもなるのではないでしょうか。
・日本の学校では、生徒指導の時に個別に生徒を呼び出して先生が話をする。今回のビデオのように、子どもたち自身が話し合いに参加する形にはなっていない。日本の学校とは異なる学校の形がとても新鮮だった。
→日本の学校では、内輪で処理をしたり、穏便にことを運んだりなど、舞台の裏側でなし崩し的に解決しようとすることが多いように思います。しかしそれは学校のせいというよりも、むしろ日本の社会のありさまが学校に反映しているのかもしれません。どこかの会社のみならず、国会のようすからさえもそう感じさせられてしまいます。
では、また!
 |
記:2004年5月28日
今回から、学校の文化について考えていきます。
まずは、日本の学校の特徴について検討しました。前回の講義の中でも、学校での持ち物や身につけるものがみんな同じであることが多いという話が出ました。それらにとどまらず、日本の学校では、学習内容もみんな同じ内容を、みんな同時に勉強しています。授業のやり方についても、多くの場合、一斉授業という形態がとられています。
私たちは、学校ってそういうものだと思ってしまいがちですが、必ずしもそんな学校ばかりではありません。そこで、日本の学校とは大きく異なる学校の姿を知り、そこからもう一度日本の学校について考えるため、フランスのフレネ学校のビデオを見ました。
フレネ学校は、異年齢集団で成り立つ学級、個々人で異なる学習内容など、さまざまな点で日本の学校と違っていました。日本のやり方とは異なるやり方も可能であること、やり方の違いの背後には、学習や学校に関する見方や考え方の違いがあることが分かりました。
次回もさらにフレネ学校を題材にして考えていきましょう。なお、次回の講義は、6月1日はみなさんが教育実習にいくため、6月8日となります。
では、みなさんのリアクションペーパーの一部を紹介します。
・個人別のカリキュラムで、しかも生徒が自ら学習計画を立てるというのは想像できません。まるで大学ではないですか。いや、大学よりも進んでいる気さえします。
→大学生になるまで待たずとも、フレネ学校の子どもたちを見ると、自ら学び考えることは小学生でも十分にできることが分かります。もちろんそれは、できるようになるためのプロセスを学校がきちんと準備しているからこそ実現可能なのです。日本でも、自ら学び考える子どもを育成することが目標になっています。しかし、フレネ学校のようすを知った今、そのような子どもを育てるためのプロセスが日本の学校の中に準備されていないようには感じませんか?
・日本では、「前へならえ」と言われれば、一斉に同じように動く。何も考えないですむ分、楽である。日本の学校を単純に「悪い」とすることはできないが、何かを創造するために「考える」ということにもっと積極的になるのもよいと思った。
→何も考えないで従うという「楽」をしていると、どんな「結果」が生じる可能性があるでしょうか。戦前の日本やドイツで、軍国主義やファシズムが大衆に支持されたことなども、「楽」をした「結果」のひとつかもしれません。現在の私たちが「楽」をしていると、後生の人々に申し訳の立たない「結果」をもたらしてしまうこともあるでしょう。そうならないためにも、「楽」をせずにきちんと考えることが必要です。そのあたりについて、エーリッヒ・フロムの『自由からの逃走』という本が参考になりますので、ぜひお読みください。
・今の自分に足りないと思うのは、自分から課題を見つけてそれを調べようとする意欲です。大学に来てから、自分がどれだけ受け身な授業態度だったか分かるようになりました。自分で考えなければならない授業は苦痛ではありますが、やり終えた後の達成感は大きいし、印象もより深く残ります。
→大学入学以前にあなたが受けた教育では、自ら課題を見つけて考えていく態度が身につかなかったということでしょうか。その代わり、自分で考えることは苦痛であるという感覚が身についてしまったのかもしれません。フレネ学校の生徒であれば、自分で考えることこそが楽しく、自分で考えずに強制されることが苦痛であると感じるのではないでしょうか。そういう子どもを育てられる教師になってくださるよう願っています。
では、また次回! 実習がんばってくださいね。
記:2004年5月19日
今回はまず、前回の続きで子育て文化の多様性についてみなさんが調べた内容を発表してもらいました。家族形態の多様性についてでしたが、サモアの家族やヘアー・インディアンの家族など、私たちの感覚とはまったく異なった家族の形があることが分かりました。
発表のためにみなさんが作ってくれた模造紙の資料を下に掲載しました。クリックすると大きくなります。
家族の多様性 乳幼児の扱い方 しつけの仕方
みなさんの発表に続いて、教師や教室の文化についてお話ししました。おもしろいことに、みなさんの調べた子育て文化と教師や教室の文化は、相似的なのでした。
権力関係に基づく垂直的なしつけをする文化のもとでは、教師と生徒との間にも同じような関係が見られます。それに対し、水平的なしつけをする日本では、あからさまな「権威−服従」ではない関係を生徒と築こうとする教師が多いのです。
その他にも日本の教師には特徴がありました。たとえば、日本の教師は教科を教えることだけではなくさまざまな場面で生徒と関わる「ジェネラリスト」であるのが普通ですが、アメリカ合州国では、教科の学習だけに職務が限定されている「スペシャリスト」なのです。
このように、私たちが当たり前だと思っている教師のありようは、きわめて日本的なものなのであり、唯一不変のものではないのです。
では、リアクションペーパーをいくつか紹介しましょう。
・「天使にラブソングを」と「陽のあたる教室」という映画を思い出しました。私はどちらもアメリカ版の「金八先生」だと思っていました。でも、よくよく思い返してみると、音楽を通して子どもたちと心の交流をしていくという点で両方ともスペシャリストでした。もう一度、映画を見返してみたくなりました。
→いいところに気づきましたね。学園ものの外国映画は、よくみると日本の教師や学校と違っているのですが、私たちは日本的なものをそこに読み込んでしまって、違いに気づかないこともあるんですね。今度からは、そういうところに気をつけて見てみることにしましょう。
・子育ての多様性のところで、生みの親の家が嫌だったら、おじさんおばさんの家に行ってもいいという家族形態があることを知って、とても衝撃を受けました。それだけ私は、日本での家庭のありかたについての固定観念が強いのかな…と思いました。
→衝撃を受けるのは別におかしなことではないように思います。衝撃が大きいことは、私たちが自分の子どもをあたかも親の「私有物」のように考えていることのあらわれなのかもしれません。もちろん子どもは誰の所有物でもないですが、現代の日本社会では、「親のもの」という感覚が強くなっているのかもしれません。それに対し、「一族のもの」と考える文化もあるでしょうし、「社会のもの(=共有物)」とみなす文化もあるのでしょう。あまりにも強く親だけのものだと考えると、何らかの弊害も生じてしまうかもしれません。
・日本の小学校の先生はたいへんすぎる。子どもたちといろいろするのは楽しいけれど、勤務時間は長すぎだと思います。教師だけではなく、サラリーマンもそうです。
→その通りですね。しかし、そのような状況は、長い不況のせいで、是正されるどころか悪化しているのが現状なのかもしれません。若い人たちの意識が会社人間化しつつあるという報道があったようにも思います。前途は多難ですね。
では、また次回お会いしましょう。
記:2004年5月15日
前回に引き続き、「子育て」について考えました。今回は、私の方から一方的にお話しするのではなく、みなさん自身が調べ、発表することによって学習しました。
今回のテーマは、「子育ての多様性」でした。多様性が存在するということは、子育てがまさしく「文化」として構成されていることを示しています。その多様性を、家族の形態自体の多様性、乳幼児の扱い方の多様性、子どものしつけの多様性という3つの側面からとらえました。
3つの班に分かれ、参考図書から得られた知見を模造紙にまとめました。1コマのなかだけやりましたので、十分な時間をかけられなかったのは残念でしたが、基本的な知識については押さえることができたように思います。
日本における乳幼児の扱い方は、欧米に比べて子ども主体のものであること、権力関係にに基づく厳格なしつけをする欧米に比べ、日本でのしつけは水平的なものであることが分かりました。また、そのような違いは、社会のありかたの違いとも関係しているようでした。
唯一絶対の子育て方法があるのではなく、それぞれの社会状況に適合するようなやり方が文化的に形作られているわけですね。また、みなさんの発表にもありましたように、時代によって変化していくものでもあるのです。
なお、家族形態の多様性に関する発表は次回にやっていただきますので、よろしくお願いします。
では、また次回。
 |
記:2004年4月27日
今回は、「子育て」について考えました。教育のことを考えていく上で、子どもをどのような存在としてとらえ、どう育てようとするかはとても重要な問題です。
子育てに関するビデオを見ながら、みなさんの意見も聞きつつ、子育てについて考えていきました。
子どもの抱き方も地域によって異なっていましたし、子育て役割を誰に割り当てるのかについてもいろいろなやり方がありました。
私たちが「こうあるべき」と考える子育てのやり方や考え方も、数多くあるうちの一つなのであり、文化として作られたものなのです。
私たちは、自分が受けてきた子育ての方法や、自分にとって身近なやり方のほうがより優れているとか、望ましいとか考えてしまいがちです。そのとき私たちは、異なった文化の間に必ずしも優劣があるわけではないのに、自分の文化への近さによって価値判断をしてしまっているのです。
これからさまざまな異文化に出会っていく私たち(それは必ずしも「外国の文化」とは限りません)は、お互いの相違を認め合い、折り合いをつけたり、新しい文化を創造したりしながら、共に生きていきたいものです。
では、リアクションペーパーを紹介しましょう。
・もし子どもができたら自分ならどうするかと考えたとき、やはりいちばんに頭に浮かんできたのは、自分が育てられた方法と同じやり方でした。これも文化なんですね。
→その通りですね。それに気づいていることが大切です。自分の考えや感覚を絶対的なものだとしてしまうと、異なっている人々と共生することが困難になってしまうからです。
・子育てのやり方ひとつとっても、違いがここまであるとは思わなかった。
→こんなに大きな違いがあることは、人間にとっての子育てのやり方が、本能によって規定されているのではないことを示していると考えることもできそうですね。
・他の方も言ってましたけど、子育てって一体どこからどこまでなんでしょう。学校に行くようになるまでどころか、大学に通っている今も、仕送りをもらっていますし、これからも何かと助けをもらうだろうなと思います。
→もちろんいつまでたっても親は親であり続けるわけです。そうではあっても、子どもは親とは自立・独立した生活を送るようになっていきます。しかし、いつから自立・独立した生活をするようになるのかは、やはり地域や時代によって大きく異なります。大学生になったら学費や生活費は親に頼らないで自分で何とかするのが当たり前という地域もあるのです。
・私も1歳くらいから保育園に行きました。両親とも仕事をしていましたが、夕方には仕事が終わり、親と一緒の時間はけっこう多かったので、よかったと思います。
→このような職場であれば、「両立」に悩む人も少なくなるのかもしれません。長時間労働が当たり前という文化がそもそもおかしいんですよね。
では、また! (^^)/~~
記:2004年4月20日
今回は、「文化から見ること」について考えました。
まずは準備として、まず私たち自身がどっぷりと浸かって「当たり前」のものと考えている「文化」を意識化し、実は「当たり前」ではないことを理解する作業をしてみました。
実際にやったのは、みなさんのこれまでの学校体験を思い出し、他の人の学校体験と比べてみるという作業でした。その結果、自分の学校体験が唯一の「当たり前」ではなく、他の人はあなたとは異なる「当たり前」を体験していたことが分かりました。つまり、みなさんの学校体験も、その地域やその時代の「文化」として作られたものだったのです。
続いて、「文化から見ることの意義」についてお話ししました。
文化いう視点から教育や学校を見るということは、私たちの教育や学校を「作られたもの」として見たり、「変わりうるもの」として見たりすることなのです。そうすることで、自分たちが「当たり前」と思っていた教育や学校をとらえなおし、新しい教育や学校を創り出すことにもつながっていくでしょう。
最後に、なぜ学校文化に注目することになったのかを説明しました。
1970年代に学校への疑問や不信がわき起こったとき、学校のありのままの姿をとらえ、新しくつくりなおしていくために、学校文化に着目するようになったのでした。
さて、今回のリアクションペーパーをいくつか紹介しましょう。
・文化とは空気みたいなもの。確かにそう思います。方言やなまりも、地元から離れていつものように話すと「ハッ?」と言われて初めて気づくのと同じですね。
→その通りですね。当たり前であればあるほど、気づきにくいのです。だからこそすぐには変わらないのでしょうね。
・自分が小・中学生だったころのことは、なかなか思い出せませんね。中学のころは校則をあんなに嫌がっていたのに、今となっては何をそんなに嫌がっていたのか、いまいち思い出せません。先生に対する不満についても、自分が先生になったら気をつけようと思っていたのに、ほとんど忘れてしまいました。教職に就く前には思い出したいものです。
→とても大切なことを思い出しましたね。今回の作業が別なところで役に立ったようでなによりです。未来のあなたの教え子さんたちのためにも、きちんと思い出しておいてくださいね。
・メロディオンが商品名だったということがたいへんショッキングでした。保育園から使っていたのに…。同じ国でも地域によって文化が違うのはおもしろいと思います。
→自分にとっての当たり前が他の人にはそうではないというのは、結構ショッキングな体験です。自分にとってかけがえがなかったり、大切だったりするものが、他の人にはそうではないとすれば、なおさらショックが大きいでしょう。文化の違いには、単なる表面上の相違だけではなく、もっと深いところでの違いも含まれているのです。
・同じ県にいても違いにとまどうことが多いので、ましてや県が違えば、いろいろあって当たり前なんですね。
→「当たり前」がいろいろあるのが「当たり前」なんですね。でも、同じところにとどまっている人たちは、違いを経験すること自体が少ないので、「いろいろあって当たり前」のほうの「当たり前」にはなかなか気づかないようです。違いに気づきあい、それを認め合えるようになりたいものですね。
では、また次回お会いしましょう。
記:2004年4月13日
いよいよ学校文化論が始まりました。どうぞよろしくお願いします。
今回は、講義のイントロダクションとして、講義の目標や予定、評価の方法などについてお話しました。また、この講義で扱う「文化」とはどのようなものなのか、簡単にお話しました。
私たちが「当たり前」だと考えている行動の仕方や考え方も、地域や時代が異なれば、必ずしも「当たり前」だとは限りません。つまり、私たちの行動の仕方や考え方は、今の時代の私たちの「文化」として作られているものなのです。
この講義では、そのような私たちの「当たり前」を問い直していきたいと思います。
では、今回のリアクションペーパーをいくつか紹介しましょう。
・自分の中の当たり前になっている文化を一度引き出してみて、みんなとの違いや同じところを見てみたいと思いました。
→それはおもしろそうですね。全部を引き出すのは難しいですが、一部だけなら可能かもしれません。ぜひともやってみることにしましょう。
・春ですね。花見には行きましたか? 今年は天気もよかったし、高田公園はきれいでしたよ。
→東京と上越とで2回桜を楽しむことができました。上越では、高田公園の脇に住んでいるので、散歩がてら高田公園の桜を鑑賞しました。たくさん出ている屋台では、焼きそばやじゃがバターを買って食べました。
では、また来週。
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Copyright(c)2004 FUJITA Takeshi. All Rights Reserved. |
|

|
|
 |