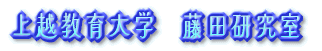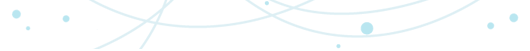|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
記:2004年11月24日
今回は、レポートの書き方についてお話ししました。
与えられたテーマについて、やみくもに材料を探すのではなく、「感受概念」をもちながら資料やデータにあたっていくことが大切です。
また、いくつかの資料を切りはりしてレポートを組み立てるのではなく、あくまでも自分なりの考えをレポートとして作り出していくようにしなければなりません。
そのために、資料などを読むなかから自分なりの考えを発展させていく方法について、実習も交えながらお話ししました。
今後もたくさんのレポートや卒業論文を書くことになると思いますが、漫然と書くのではなく、今回お話ししたことを参考にしてやってみてください。
では、今回のリアクションペーパーをいくつか紹介します。
・今回の講義で読んだ文章を吟味して、目に見えるものだけで「今の子どもたちは……」と判断してはいけないと思いました。「今の学校」も「昔の学校」も、同じくらいまじめだったり、同時にすさんでいたりするのではないか、と思ってしまいました。
→そうですね。マスコミで流されている子どもイメージや学校イメージだけで語ることがとても危険であることを理解していただけたようです。実際の子どもを目の前にしていたとしても、思いこみやイメージによって、実際の姿を見逃してしまうこともありますので、注意する必要があるでしょうひとの。
・「本当か?」という吟味のスタンスを持てるようになったのは最近で、大学に来たからだと思います。そのスタンスに加えて、自分の意見を言うこと、普段の生活から疑問を持つことなど、いい意味での「ひねくれ者」になりたいと思いました。
→独我的ではなく、建設的な批判を通して、考えや意見をより深めていくことができるといいですね。批判のための批判ではなく、新しいものを創り出していくための批判でありたいものです。
・これまで批判的に考えるということをあまりしていなかったような気がしました。偉い人(?)が書いているからと、最初から批判的に考えようと思っていなかったのかもしれないです。でも今回のように、自分が何となくおかしいなと思ったことについて、もう少し掘り下げると、そこから次の疑問が出てくるということに驚きました。
→批判のための批判に終わらないためにも、「もう少し掘り下げる」ということが大切なんですね。おかしいなと思ったならば、そのタネをどう自分なりの考えに発展させられるかがミソなのです。そのように普段から心がけることによって、考えるためのたくさんのタネを集めることができるでしょう。
では、また次回お会いしましょう!
記:2004年11月16日
今回は、社会集団への着目という手法によって、学歴社会についてさらに考えていきました。
近代社会の理念を達成するために導入された学歴社会も、社会集団ごとに分けてさまざまな点から吟味してみると、実は、近代社会の理念とは必ずしも一致していないことが分かりました。
欧米と異なり、その点については、あまり日本では問題にされてきませんでした。それよりも、教育的な問題や、学歴で測られる能力と仕事で必要とされる能力のギャップなどが問題にされてきたところに、日本の特徴があります。しかし日本でも、今後ますます社会的格差が拡大していくことが予想されていますので、近代社会の理念の達成という問題についても考えていく必要があるでしょう。
最後に、どうして現在の日本では学歴社会というイメージが未だに維持されているのか、いくつかの側面から考えました。そこからは、学歴社会イメージとは、社会の問題であると同時に、私たち一人ひとりの問題でもあることが
見えてきました。
さて、今回のリアクションペーパーを見てみましょう。
・成績と家庭の収入などとの間に相関関係があるのには驚いた。しかし、本人のやる気が一番大きく影響しているのではないかとも思った。お金がなかったとしても、本人のやる気さえあればどうにかなるのではないか。
→もちろん本人のやる気は大いに問題です。しかし、本人のやる気のせいだとすると、こういう相関が出てこないはずなのです。ですから、家庭の収入などの問題は本人のやる気にも影響を与え、その結果として成績に違いが生じていると考える方がいいのではないでしょうか。最近では「インセンティブ・ディバイド」として、本人の意欲も階層によって異なっていることが指摘されています。その点については、次の文献が参考になります。
苅谷剛彦『階層化日本と教育危機』有信堂、2001年。
・他者との差異化をするためのブランド品獲得競争としての学歴競争が、どうして学歴社会イメージが維持されるしくみとつながるのでしょうか。
→お受験などに象徴されるように、一流大学というブランドを獲得するための競争が一部の人たちによって行われていることによって、実際に学歴社会であるかどうかとはかかわりなく、現在の日本は学歴社会なんだなというイメージが多くの人たちに抱かれるようになるということです。おそらくマスコミなどによってそういったイメージが広範に流布されていことも大きく影響しているのではないでしょうか。
では、また!
記:2004年11月2日
今回は、相対化という手法を用いて学歴社会に関する一般的見解を吟味しました。
現代の日本は、タテの学歴の違いによって所得にも大きな違いが生まれたり、高い学歴を多くの人々が求めていたりするような「学歴社会」だと言えるのかどうか、他の国と比べてみました。また、ヨコの学歴が進学や就職に決定的な影響を及ぼすような「学歴社会」なのかどうか、データによって調べてみました。その結果、今の日本は私たちがイメージしているような学歴社会とは異なっていることが分かりました。
また、学歴によって所得や社会的地位が決まる学歴社会と、それ以前の社会と比べてみることによって、「学歴社会」の意味について考えました。その結果、学歴社会を単純に悪者として決めつけることは難しいことが分かりました。
このように、相対化という手法を用いると、私たちが当たり前だと思っていることを見直してみることができるのです。
さて、重要なお知らせです。次回の11月4日(木)講義は都合のため休講にします。
では、今回のリアクションペーパーをいくつか紹介しましょう。
・最近では、どこの大学を出たかより、大学で何を学んだかが重視されていると言われています。個々の能力を見るということだと思います。しかし、講義のなかでは能力が学歴とイコールのように扱われていたので、その辺りがよく分からなくなってしまいました。そもそも学歴とは、大学などのネームバリューみないなものだと思っていたのですが、違うのでしょうか。
→今回の講義では、個々の能力を見るのに「学歴」というメガネを使う「学歴社会」について考えたわけです。能力を学歴とイコールのものとして扱ったのではなく、能力を学歴で測る社会について扱ったのです。ですから、学歴というメガネを用いない社会については扱っていません。能力を学歴で測る「学歴社会」では、学歴は単なるネームバリューの問題ではなく、ネームバリューの高い大学の学歴を得る受験競争に勝ち残ることが能力の高さを示していると見なされることになるでしょう。なお、講義のなかでも何回も言いましたが、私自身が能力とはそういうものだとか、そのような社会であるべきだとかと考えているわけではありませんので、念のため。
・学歴主義に対する見方が変わりました。本人の努力ではどうしようもない部分まで測られて否定されたとしたら、人としてどうかなと思います。本人の努力でもしかしたら何とかなりそうな「学歴」の部分だけを否定されるほうが、まだ生きていけそうな気がします。
→入学試験では、学力という一部分だけではなく、さまざまな側面からその人を判断するべきだというのはよく言われることですが、あなたのおっしゃるように、さまざまな側面を測った結果として不合格になるほうがつらいかもしれません。それよりも、一部分だけ測った結果であるほうが、その他の部分に期待を持ち続けられますよね。
・実際には、学歴は1人の人間に対してどの程度影響するのでしょうか。相対化といっても、1人しかいない人間に対して比べることはできないので、本当のところは分からないのではないだろうか。たとえば、Aさんが高校卒だった場合と、大卒だった場合というのは、現実にはどちらか一方しか起こらないので、比較はできません。
→おっしゃるとおりです。1人の人間については、1つの場合以外のことは起こりませんので比較はできません。しかし、社会学ではたくさんの人の相互関係の中にどのような仕組みが存在しているのかを考えます。つまり、高卒だった人たちと、大卒だった人たちではどんな違いがあるのかを比較し、全体としてどんな傾向があるのかを考えようというわけです。
では、また。次の講義は11月11日です。
記:2004年10月26日
前回に引き続き、少年非行に関する一般的見解を吟味しました。今回は、「理論」について学習しました。
ここで言う理論とは、「社会的現象のしくみや成り立ちに関する説明」のことです。
「〜すべきだ」といった少年非行に関する対処法には、その背後に少年非行のしくみに関する「理論」が隠れていること、背後にある理論が異なれば、「〜すべきだ」という内容も変わることが分かりました。
おなじ「少年非行」という社会的現象でも、注目するところや力点が異なると、いろいろな説明の仕方(=理論)が可能であることも分かりました。
ですから、一般的見解をそのままうのみにするのではなく、別の説明の仕方があるかもしれないと考えることが重要ですし、社会的現象の理解を深めるためには、さまざまな理論を知っていることが有益なのです。
では、みなさんのリアクションペーパーをいくつか紹介します。
・今回の講義で学ぶべきことは、それぞれの理論のよしあしではなく、さまざまな理論を学ぶということですよね。
→その通りです。この理論はよくてこの理論はよくないと言いたかったのではありません。それぞれの理論は、説明しようとしている範囲が異なっています。いわば「得意分野」が違っているということです。そのことをきちんと理解しつつ、さまざまな理論を学び、対処法のレパートリーも増やしてもらいたいと考えています。
・今回の講義のなかで、そもそも「非行」という行為自体がどうして起こったのかに興味を持ちました。また、どこからどこまでの行動が非行なのでしょうか。
→同じような行為であっても、時代や社会、地域が異なれば、非行であったりそうではなかったりする可能性があります。「非行」という行為自体があるのではなく、非行だとみんながみなすから、ある行為が「非行」になると考えることができるのです。もしそうならば、非行という行為が起こるのではなく、非行とみなされる行為がなされることになりますし、どの行為を非行とみなすかは、時代や社会などによって異なるということになります。
・緊張理論の中身は分かったのだが、なぜ「緊張」という文字があてはまっているのか分からなかった。
→たとえば、成功したいという欲求があるのにそれを達成する手段がないという場合に葛藤や欲求不満を感じます。そのような状態を緊張状態として言い表していると理解してください。
では、また次回!
記:2004年10月21日
今回は、少年非行に関する一般的見解を吟味することを通して、教育社会学における「実証」について説明しました。
マスコミなどで流される一般的見解をそのままうのみにするのは危険であること、また、根拠やデータについてもさまざまな角度から吟味できることが理解できたのではないでしょうか。
今後は、みなさん自身が、さまざまな見解や、根拠やデータについて吟味していきましょう。ただしそれは、マスコミや他人の見解についてだけではありません。みなさん自身の意見についても同様であることを忘れないでおいてください。
では、今回のリアクションペーパーを紹介します。
・私は神戸の連続殺人事件の犯人と同じ年生まれで、「キレる17歳」と呼ばれていた世代でした。今回の授業で、多少そのあたりのわだかまりが解消したこと、「自分の目で見て、自分の頭で考えること」の大切さを再認識できたことが収穫でした。
→それはなによりです。その他のわだかまりの解消に向け、さらに自分自身でもいろいろと調べ、考えていってくださることを期待しています。
・前に大学の授業で、データに基づいたレポートを書いたことがあるが、そのとき使ったデータの「集計方法」の欄は、なぜ書いてあるか分からず、飛ばし読みしていた。今回の授業でなぜ書いてあるかも分かったし、そこにも目を向けていかなければならないとも感じた。
→調査方法や集計方法は、調査を読み取る上でとても大切なものなのです。そのあたりを自覚して、さまざまな調査の結果自体を吟味しましょう。特に、調査方法が書いてないものは要注意です。
・少年犯罪は、家庭の核家族化などによる教育力の低下や、道徳をうまくできる先生が少なくなったことなどが要因ではないか。また、インターネットなどの普及により、犯罪サイトなどを子どもが手軽に見られるようになったことも要因の一つではないだろうか。
→もしかするとそうかもしれません。しかし、あなたの見解もまた、きちんとした根拠やデータによって吟味しなければなりません。そのためには、どんなデータが必要でしょうか。ちょっと考えてみてください。
では、また!(^^)/
記:2004年10月12日
教育社会学の授業が始まりました。この授業では、「教育社会学する」ことによって、教育社会学の見方・考え方を身につけていくことをねらいにしています。
今回は、教育社会学とはどのようなものなのかについて概略をお話ししました。
まず、教育社会学のイメージを心理学と対比させながら説明しました。ムスリムの男の子の話を題材に説明したように、ある現象について心の問題として考えるのではなく、人間関係のしくみや社会のありようの問題として考えることもできます。それが社会学なのです。
最近の日本社会では、さまざまな問題を個人の心と結びつけて考えることが多くなってきました(=社会の心理主義化)。しかし、それ以外のとらえかたも可能なのですし、学校現場の先生たちも、知らず知らずのうちに社会学的なとらえかたをしていることも多いのです。
続いて、教育社会学の特徴を三つお話ししました。一つめは「実証」ということ、二つめは「相対化」ということ、三つめは「社会的構築」ということでした。今後の講義では、これらの特徴について具体的なトピックを題材にして説明していくことになります。
では、今回のみなさんのリアクションペーパーをいくつか紹介しましょう。
・心理学的に、「この人は心の中がこうだから…なのかな」と考えることが多かったのですが、社会学的に考えると全く違った見方ができると分かり、そのような考え方でものごとや人をみるのも大切だなと思いました。
→もちろん心理学的に考える必要もあるでしょう。しかし同時に、社会学的にも考えることによって、より深くものごとをとらえることができるようになると思います。興味をもっていただけたようですので、ぜひとも社会学的な見方・考え方を身につけるよう頑張ってください。
・事実学と規範学という分け方を知り、おもしろさを感じました。これまで規範学の授業を多く受けてきたので、事実を探ることのおもしろさを感じられる分野だと思いました。
→教育について語るときには、「どうすべきか」という語り方になってしまうことが多いように思います。「どうすべきか」を論じるときにも、きちんと「どうなっているか」を踏まえておかないと、おかしな方向に行ってしまうこともあるのではないでしょうか。教育はもちろん、その他の話題についても、根拠やデータに基づいて語るように心がけてみてはどうですか。
・教科書や参考書は必要ですか。
→教科書は必要ありません。その代わり、毎回の講義では、その講義内容をよりよく理解するため、発展的に理解するための参考文献を紹介します。みなさんの興味に応じて、それらの参考文献を読んでみてください。
では、また。
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Copyright(c)2004 FUJITA Takeshi. All Rights Reserved. |
|

|
|
 |