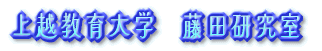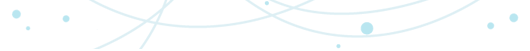|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
記:2004年12月3日
2週間ぶりの講義でした。前回に引き続き、女性をめぐる問題について考えました。
記:2004年11月12日
今回は、女性をめぐる問題について考えました。
現代の日本では、男女共同参画社会基本法も制定され、性別による分け隔てなく各々の個性や能力を発揮できる社会の実現を目指しています。
しかし現実には、性別役割分業の考え方や習慣が色濃く残っており、女性が「生きやすい」社会になっているとはなかなか言えないのが現状です。
性別役割分業は、社会的に作られた性秩序(ジェンダー)がその背景にあります。性別という箱のなかに、人間を振り分け、その箱にふさわしいとされる振る舞い方を強制しているわけです。しかし、人間はそれぞれ違っているのですから、決められた箱に振り分けて生き方を制限するのではなく、その人らしさを十分に発揮できるようにしたらいいのではないでしょうか。特に、その箱によって苦しめられている人々のことを考えるならば、なおさらです。
では、今回のリアクションペーパーを紹介します。
・ビートたけしは、著書のなかで「女性が、女性の権利の主張を男性に手伝ってもらったり、男性に頼っている時点で、実質的な男女平等はありえない」と述べています。このような社会が形成されてしまった今、ジェンダー問題の解決はとても難しいことなのではないでしょうか。
→ビートたけしの文章をちょっと読み替えてみましょう。たとえば、「障害者が、障害者の権利の主張を健常者に手伝ってもらったり・・・」、「黒人が、黒人の権利の主張を白人に手伝ってもらったり・・・」、「いじめられる側だった子が、いじめられる側の権利の主張をいじめる側だった子に手伝ってもらったり・・・」、「A国の攻撃によって殺される側のB国の一般市民が、B国の一般市民の権利の主張をA国の市民に手伝ってもらったり・・・」という具合です。何かおかしくはないでしょうか。差別する側が、差別されている側の援助をすることがなぜいけないのでしょうか。差別する側だった人々が、差別される側の人々と共同して差別の撤廃を目指した運動を行うのはおかしなことなのでしょうか。むしろ、そうすることこそが当然のことなのであり、そうしないことのほうが普通ではないおかしなことではないかと思われるのです。
・先生が講義中におっしゃっていたドラマ(たぶん「アット・ホーム・ダッド」だと思います)は、私も見ていて、実際ほとんどの男性はあのドラマの主人公ような考え方なのだろうと思いました。でも、今日の講義で、それぞれの国によって男女のとらえかたが非常に異なっていたのは、おもしろいと思いました。
→国によって違うということは、まさに性別の秩序(ジェンダー)が、社会的に作られていることを示しているんですね。社会的に作られているということは、他の国に見られるような別の作り方もありうるということですし、今後、作りかえていくこともできるということですよね。作りかえるという選択肢があること、私たちにその力があることを忘れないようにしたいものです。
・たまに女性雑誌などで、男の人は競争社会のなかで生きていかなければならないので大変だという話が載っていたりしますが、女性は競争社会のなかにいないのでしょうか。同じ土俵のうえで暮らしているのだから、女性の側も壁を作らない方がいいと思いました。
→その雑誌の記事は、まさに性別役割分業の考え方によって書かれていたのでしょう。性別役割分業という考え方や習慣は、何も男性だけではなく、女性によっても維持されているのです。また、あなたもおっしゃるように、競争社会のなかにいるのは男性だけではありません。男性だから競争社会のなかにいるのではなく、性別に関係なく競争社会にいるのですから、なにもあえて男性か女性かというカテゴリーを持ち出す必要はないのですね。
・男性と女性とではそれぞれに限界があるのだから、昔くさい考え方かもしれませんが、私個人としては、女は家、男は外で働くというのが一番の策だと思います。しかし、逆のパターンを行ったとしても普通だねと違和感がない社会づくりをしていくべきだと思います。
→なぜ男性と女性にそれぞれ限界があると考えなければならないのでしょうか。私という個人に限界があって、あなたという個人に限界があるという考え方ではどこがまずいのですか。実際、私は柔道の谷亮子選手には絶対にかなわないですが、それは私が男性だからでも、谷選手が女性だからでもなく、それぞれの個人としての能力に違いがあるからということではないでしょうか。なぜ、強迫的に男女に分けなければ気がすまなくなってしまっているのでしょうか。
では、また!
記:2004年11月8日
今回は、前回に引き続て差別と不平等の問題について学習しました。
前回の講義で、差別のしくみをとらえる図式についてお話ししました。その図式を用いることで、さまざまなタイプの差別があることが分かりました。また、差別的ではない関係を作っていく手がかりとして、相手を知ることの重要性が浮かび上がってきました。
そこで、相手を知るとはどのようなことなのか、また、違いを理解するとはどのようなことなのかを実感するためにビデオを見ました。
私たちが独自な世界を作り上げているのと同じように、ビデオで見た人々も独自の世界を作り上げていました。それは、一方が他方に従属するような関係ではなく、お互いに対等なものであるはずですが、なかなかそのように意識することはできなかったのではないでしょうか。それこそが、気づかないうちに陥っている差別のしくみなのです。自分自身も差別的であると気づくこととが反差別への出発点なのではないでしょうか。
では、今回のリアクションペーパーを紹介しましょう。
・先生は、講義の最後に、自分と違う人について理解しようと言っていたけれど、それだけでいいのだろうか。理解したという思いこみで接すると、ますますおかしくなるのではないか。
→おっしゃるとおり、理解したという思いこみだけでは困りますよね。そうならないためには、理解というのは一方的にするものではなく、相手との関係のなかでそのつど少しずつ協働的に作っていくものだと考えたらどうでしょうか。つまり、理解とは常に未完成のものなのであり、相手との相互関係のなかで絶えずつくりかえられていくものだととらえるということです。
・自分がいかに何も知らないかを感じさせられるビデオだった。ろう者と聴者のお互いのコミュニケーションの壁を低くし、理解し合おうと努力することは大切なことだと思う。それにしても、自分がとても狭い世界に生きていたことを痛感する。
→ビデオを見ていただいたかいがありました。自分を取り巻く世界はもっと広いんだ、知るべきことはもっとたくさんあるんだと考えた方が、好奇心をもって楽しく生きられるのではないでしょうか。また、ろう者と聴者のコミュニケーションの壁を低くしなければならないのは、とりもなおさず聴者なのだろうと思います。
・同化的差別ということが言われたが、同じなので同じルールにするというのは問題がないように思える。もちろん違いを認めずに同化を強要していることもあるのかもしれないが、同じならば違いがないはずなので、なんだか納得がいかない。もう少し補足説明をしてほしい。
→分かりました。「同じ」という言葉がキーワードです。講義で用いた「同じ」という言葉は、「同じとみなす」という意味なのです。実際に同じかどうかということではなく、同じとみなすかどうかということです。ですから、同化的差別の場合には、違いがあるにもかかわらずそれを認めないで同じとみなすということになります。そして、その決定はマジョリティー側によって一方的になされるのであり、マイノリティー側の意見は聞いてもらえないのです。
では、また次回!!
記:2004年10月27日
今回からは、生涯学習の具体的な学習課題について学んでいくことになります。生涯学習について学ぶというよりも、生涯学習をしてみることを通して生涯学習を学ぶということになります。
これからとりあげていく学習課題は、社会参加としての生涯学習に該当するものです。生涯学習を進めていく際はもちろん、日常の社会生活のなかでも直面する社会問題について学習していきます。それを通して、みなさん自身に、よりよい社会の構築に向けた知識を蓄えていってもらいたいと考えています。
今回は、差別と不平等について学びました。日頃あまり意識することはないかもしれませんが、現代の日本にもさまざまな差別や不平等の問題が存在していることが分かりました。
また、アメリカにおける反差別の実験授業のビデオからは、ごく普通の子どもたちのなかでも、いとも簡単に差別が生じてしまうことが見てとれました。
最後に、さまざまな差別においてどのようなことが生じているのか、差別のしくみについて考えました。
次回も引き続き、この問題について考えていきます。では、今回のリアクションペーパーを紹介します。
・差別について考えたとき、あまりたくさん思い浮かべられなかったことがショックだった。日本でも意識しないで差別していることがあると思った。
→差別についてあまり知らない、あるいは、意識していないということ自体が、差別をなくすことができない原因になっているかもしれません。もちろんすべて知ることも、常に意識していることもできないでしょうが、そのように努力しようという姿勢は大切であるように思います。
・さっきまで一緒に遊んだりしていたはずなのに、子どもたちの態度が急変したのに驚いた。たった一つの、しかも不確かな情報だけで判断して差別していた。その情報をうのみにしたことが差別となってあらわれてきたことが興味深かった。
→その通りですね。とても大切なことを指摘してくださったように思います。差別をするのは決して特別な人ばかりなのではなく、ごく普通の人なのです。また、不確かな情報で判断すること、情報をうのみにすることはとても危険なのです。
・今日の講義のなかにでてきた「差別のしくみ」は、思っていたよりもシンプルで、自分や周りの言動を振り返る際に思い出したいと思った。
→どうもありがとうございます。講義でお話しした図式は、おっしゃるように、差別に関してだけではなくさまざまなところで用いることができると思います。その点についてもっと詳しく勉強したい方は次の文献が参考になるかもしれません。
藤田武志「反差別の授業の構築に向けて ―『青い目 茶色い目』の授業の社会学的考察をとおして―」日本教育方法学会編『教育方法学研究』第21巻、1996年。
では、また次回!
記:2004年10月25日
今回は、前回に引き続き、生涯学習の現状と課題というテーマでお話ししました。
まず、生涯学習をめぐる国の政策の変化についてお話ししました。その変化には、学習機会の格差を拡大してしまう可能性もあることが分かりました。
続いて、地方自治体における生涯学習の実際について、上越市を例にお話ししました。上越市の生涯学習に関する情報誌を配布しましたので、みなさんもぜひ参加してください。なお、上越市の生涯学習に関する情報はココをクリックすると見ることができます。
最後に、生涯学習の新しい動きについてお話ししました。学習資源や学習方法、学習場所などにおいて、さまざまな新しい試みがなされています。それらは、学校教育にも応用できるものも少なくないでしょう。
では、今回のリアクションペーパーを紹介しましょう。
・上越市の生涯学習のパンフレットを見て、参加したい講義や活動がいくつかあった。ふだん目にしない情報がたくさん入ってきてよかった。
→前回の講義でも生涯学習の阻害要因として、情報がないことを挙げましたが、やはり生涯学習に関する情報は「ふだん目にしない」のですね。この方以外にも、多くの方が同じような感想を書いていらっしゃいました。情報の問題は大きな課題です。
・生涯学習の情報について、自治体側だけではなく、参加する側も協力して広めることができればいいと思う。
→情報を広める手段についてアイディアを出してくださいました。お配りしたパンフレットを見て、みなさんもいろいろな活動に参加するとともに、それをさまざまな人に広めていく活動もしてくださると幸いです。
・今回の資料に載っていた団体の活動の一部に学生ボランティアとして参加したことがあるのですが、子どもたちとふれあうことができたとともに、お母さん方とも話すことのできる機会があり、とてもよい経験になりました。また参加したいと思います。
→まさに生涯学習を実践なさっているということですね。ぜひとも今後もさまざまな活動に参加してみてください。
・今日の講義を聞くと、結局、どのような制度をつくっても問題がなくなることはないのではないかなと思いました。
→もちろん「完全な制度」を作るのは難しいと思いますが、一つ一つ問題を解決しながら、よりよい制度を作り上げていく営みこそが大切なのかもしれません。その営みに参加することも、生涯学習だと言えるでしょう。
では、また!!
記:2004年10月19日
今回は、生涯学習の現状と課題についてお話ししました。
生涯学習とはどのようなものなのか、生涯学習への参加はどんな状況なのか、生涯学習についてどのような問題があるのか、そもそも生涯学習はどうして必要なのか、といった問題について考えました。
生涯学習は、個人的次元と社会的次元の二つの点からとらえることができます。そう考えた場合、大学での学習活動とは別に、みなさん自身もすでにさまざまな学習活動にとりくんでいることに気づいた方も多いのではないでしょうか。生涯学習とは、実はとても身近にあるものなのです。
では、みなさんのリアクションペーパーの一部を紹介します。
・自己実現の意味でしか生涯学習を考え方ことがなかったけど、社会参加の意味もあるのだということを知った。
→自分の暮らしや人生の充実だけではなく、自分の住んでいる地域や関わっている人々の充実のためにできることを実行していくことも生涯学習なのですね。また、社会に参加することは、自己実現をはかることにもつながるでしょう。社会参加としての生涯学習を進めていくためには、今後の講義で扱いますが、社会について理解を深めることが役立つのではないでしょうか。
・指導者というのは裏返せば学習者になると思いますが、いかがでしょうか。
→その通りですね。指導者自身も学習活動のなかでさまざまなことを学んでいます。指導することや学習事業を企画すること自体が、学習するための資源となっているわけです。そのことをきちんと自覚しながら指導することも必要なのかもしれません。
では、また。
記:2004年10月12日
いよいよ生涯学習概論Bが始まりました。
この授業では、生涯学習のなかで重要な学習課題をいくつかとりあげ、それらを学習することを通して、生涯学習とはどのようなものなのかをみなさん自身に考えていただくことを目標にしています。
講義のなかで曜日や時間の変更についてお話しましたが、結局、変更はしないことにしましたので、予定通り火曜3限で行います。
では、頑張っていきましょう。
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Copyright(c)2004 FUJITA Takeshi. All Rights Reserved. |
|

|
|
 |