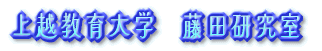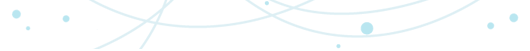|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
記:2004年7月16日
本講義のレポート課題を出題しました。ココをクリックすると、PDFファイルで見ることができます。Adobe社のAcrobat
Reader を用意してください。なお、提出期限は2004年9月9日(木)です。私の研究室のドアに封筒をはっておきますので、そこに提出してください。なお、当日の授業は時間と場所を変えて行いますので、レポート提出時に、はり紙をご覧ください。
では、今回のリアクションペーパーを紹介します。
誰に向かって言うかによって、同じ言葉でも意味が異なる
→「迷惑をかけるな」迷惑をかけている子、迷惑なんかこれっぽっちもかけていない子
記:2004年7月13日
今回は、学校と地域との関係について考えました。
学校と地域の双方にメリットがあるような関係、地域の人々とその地域の複数の学校が協力しあう関係など、ユニークな関係を作り上げている事例のあることが分かりました。
それらの事例では、学校の役割や位置づけがちょっと違っていたように思います。そこに通う子どもや勤めている教師だけのものとしての学校ではなく、「教育の縁」でさまざまな人々がつながり合うためのセンター(中心)としての学校でした。
学校と地域との関係を新たに紡いでいくためには、根本的な発想の転換が必要なのではないでしょうか。それが実は、学校や教師にとっても有益であるかもしれません。
次回は、夏休み前の最後の講義となります。次回までの課題は次の通りです。子どもをどのようにとらえるのかについて考えます。
・加藤哲夫『市民の日本語 ―NPOの可能性とコミュニケーション―』ひつじ市民新書、2002年。
・ロジャー・ハート『子どもの参画 コミュニティづくりと身近な環境ケアへの参画のための理論と実際』萌文社、2000年、27-50頁。
では、みなさんのリアクションペーパーをいくつか紹介します。
・何かをしつづけるためには、思想が必要だということを感じました。どこでも似たようなことをしているのにうまくいかない、「秋津の実践」がいいからまねしてみようとしてもうまくいかない、というのは、思想がないからではないか。
→行われている様々な取り組みは、結局のところ何を大切にしているから行われているのか(=思想)を理解せずに、取り組みだけを表面的に採り入れたとしてもうまくいかないのでしょうね。そういう確固とした思想があるならば、地域住民だけでなく、新しく赴任してきた教師たちに対してもさまざまな取り組みの意味を説明できるでしょうし、取り組みを継続・発展させることもできるのではないでしょうか。
・私の勤めている地域の、特に普通高校は受験進学指導にのみ力を入れて、地域との連携より、「国公立大○○名入学」というように予備校化してしまっています。教育コミュニティをつくったり、「学社融合」に取り組んだりすれば、受験勉強だけではない学校らしさや明るい学校を創造できるのではないかと考えました。
→少子化時代の現在、受験地獄は過去の話になるという予想もありましたが、そうではなく、さまざまな地域において有名大学進学率の上昇などがあからさまに目指されるようになりました。東京都では、数値目標を明示する高校まであらわれたようです。なかなか変化しないと批判される教育の世界において、一昔前であれば忌避されたであろうことがあっさりと導入され、広まっているという大変化が生じていることには、まったく驚かされるばかりです。
・理想的な学校・地域の報告を読ませてもらい、ためになった。しかし、忙しい学校の日常を考えると、新しいこと、エネルギーのいることは、敬遠されてしまう。とはいえ、理想の姿を描くことができなければ目的は達成されないので、そのためのやる気は失わないようにしたい。その点、講義の中に出てきた「地域の共通課題」という考え方は面白いと思う。何らかの課題は必ずありうるわけで、課題があれば対策があり、行動や活動があるでしょう。何をしたらいいかと悩むよりも、課題を見つけるということが大切だと思いました。
→どういう子ども、どういう学校、どういう地域になってほしいのか、というビジョンを描くことは大切なのでしょうね。さまざまな活動が単発で終わらずに、地域の教育課題の設定や、共有化と結びついていくならば、いい循環が生まれてくるのかもしれません。
・昔は人々が地域にどっかりと根を下ろし、学校とがっちりとつながっていたと思う。でも、それが果たして「古きよき時代」だったのかと考えると、かなり疑問である。地域も学校も日々変化していると思うし、その時代にあったつながりを考えていかなければならないと感じた。
→かつて、PTAは地域のボスが牛耳り、学校のさまざまなことに口を出すこともありました。そのような事態は、PTAならぬ「BTA」として揶揄されていました。つまり、「古きよき時代」とは言い難い時代もあったようです。講義のなかでご紹介した岸さんの別の本には、PTA改造についての話も詳しく出ていますので、ぜひ読んでみてください。
では、またっ!
記:2004年7月13日
またもや1週遅れの更新となってしまいました。貧困世帯における教育のようすについて考えました。
貧困は、全体的に豊かな社会である現在でも(あるいは、だからこそ)、切実な問題です。貧困は、単に経済的な問題であるだけではなく、学校や学習への構えや将来展望にまで影響を及ぼしています。
そういうハンディキャップを背負った子どもたちに、学校や教師は何ができるのでしょうか。そういうハンディキャップはないものとみなして、どの子にも同じように接するならば、ハンディキャップによる格差が埋まらないだけでなく、格差が拡大してしまう可能性もあるのです。
もちろん、福祉事務所や児童相談所、保護司などの仕事を教師もするべきだというわけではないでしょう。しかし、教師だからこそできること、学校だからすべきことは何なのかをきちんと考え、実施する必要はあるように思います。
次回の課題は次の通りです。地域と学校の関係について考えます。
・岸裕司『「地域暮らし」宣言 ―学校はコミュニティ・アート―』太郎次郎社エディタス、2003年、14-40頁・80-128頁。
・大阪大学大学院池田研究室編『協働の教育による学校・地域の再生 ―大阪府松原市の4つの中学校区から―』2001年、35-45頁・123-164頁。
では、今回のリアクションペーパーを紹介します。
・学校が社会階層を再生産しているというよりも、もっと大きな社会の構図のようなものが再生産しているような気もします。
→社会学では、学校が直接的に社会的不平等を再生産していると考えるのではなく、社会的不平等の再生産にさまざまな形で荷担していると考えています。ブルデュー、ボールズとギンティス、バーンスティンといった社会学者たちが、それぞれ独自の理論を提出しています。入門的なところを知りたいようでしたら、次の文献が役に立つと思います。
志水宏吉「学校文化論のパースペクティブ」長尾彰夫・池田寛編『学校文化 ―深層へのパースペクティブ』東信堂、1990年。
・社会階層の差は、実は、子どもの努力(意欲)さえも規定してしまうという事実はたいへんショッキングなことであった。
→最近では、意欲の格差はインセンティブ・ディバイドとして指摘されています。その点については次の文献を参考にしてください。
苅谷剛彦『階層化日本と教育危機 ―不平等再生産から意欲格差社会へ―』有信堂、2001年。
・とても重いテーマでした。学校では、「家庭が〜〜だから仕方ないや」という目で見てしまうところがあると思います。しかし、学校だけでは手に負えない場合でも、学校では何ができるか、できることなんかあるのか考えてみることも大切だと思いました。
→家庭のせいにしてしまうことは、家庭に全責任を負わせてしまうことでもあります。しっかりとした強い家庭であればそれでもいいのかもしれませんが、弱い家庭であればあるほど、責任の重さに堪えられない可能性が高くなります。そのしわ寄せは子どもにいくことを考えれば、家庭のせいにすることは、子どもの最善の利益にかなっていない場合もあるでしょう。その場合、共同の子育てをどう組み立てていけるのかを考える必要があるのかもしれません。
 |
記:2004年6月28日
今回は、教師の生活や人生について考えました。課題の諸論文は、それぞれライフヒストリー、ライフコース、ライフサイクルという3つの点から教師について検討していました。
ライフヒストリーを用いた研究からは、教師の仕事には私生活のありようが大きく影響していることが分かりました。ライフコース研究からは、生きる時代の特徴が意識や行為に影響している教師の姿を見てとることができました。ライフサイクルに関する研究では、職務の中に埋め込まれた立場の変化が教師に大きな影響を及ぼしていることが示されていました。
このように、教師たちの仕事や生活は、個人的なこと、時代的なこと、職務の構造といった要因と切り離すことができないのです。
たとえば、教師が大量に採用された時代の教師は、同世代からのサポートをより多く受けられたからこそさまざまな困難を切り抜けられたのかもしれません。そのことを見逃してしまうと、同世代の仲間の少ない現在の教師たちがなかなか壁を乗り越えられない姿を、個人の力のなさと錯覚してしまうことになるでしょう。
また、個人的なことに影響されない教師を「あるべき姿」とすると、たとえば、子育てを妻に押しつけて仕事に精を出す男性教師こそが望ましい、ということになってしまいます。子どもを育てる営みの一環である学校での仕事が、子育て放棄の上に成り立つという矛盾を見逃してしまいかねません。
なお、子育ては個人的なことではなく、社会の新たな構成員を育成するという、社会を再生産していくために不可欠なことがらだという考え方もあります。そう考えると、子育ては非常に社会的なことがらなのであり、それを放棄することはまさに非社会的な行為であることになるわけです。
いずれにせよ、教師のありのままの姿をとらえるところから出発する必要がありそうです。
では、次回の課題です。子どものおかれた状況、特に、普段はあまり主題的に語られることのない、貧困家庭の子どもについて考えます。
・久冨善之編『豊かさの底辺に生きる 学校システムと弱者の再生産』青木書店、1993年、3章、4章。
・青木紀編『現代日本の「見えない」貧困 生活保護受給母子世帯の現実』明石書店、2003年、第2章。
さて、今回のリアクションペーパーをいくつか紹介しましょう。
・ライフサイクルにおける危機については、性差も大きいと思いました。男性教師の場合、管理職を目指さない教師は意欲がないと思われてしまう傾向があるようです。そのため、自分の思いとは別に管理職試験を受けている人もいます。そのような人の危機感や葛藤はなおさら大きいと思います。また、採用数が減少しているので、いま入職された方はその年代になるころには、ほとんどの人がこの葛藤を抱える状況になってくると思います。
→現在の初任者が管理職になるころは、現在の性差が続くならば、ほとんどの男性教師が管理職へということにもなりかねません。しかし、必ずしも管理職に適している人ばかりとは限りません。そのため、もしかすると「民間人校長」や「事務職から校長へ」という今の動きは、そのような事態への対策として考えられているのかもしれませんね。
・いま校長などになっている世代の教師たちは、学生運動などが盛んな時代を経験していて、社会のことについてずいぶんと考えたのではないかと思うのですが、いまは社会のことを見る視点が欠けているから、社会変動に対する対応が後手に回っていくのではないかと思いました。
→現在では、社会全体の「心理主義化」が事態に拍車をかけているようにも思われます。社会的な問題であるにもかかわらず、個人の問題、心の中の問題にしてしまって、社会の矛盾には目を向けない傾向が強くなってきているのではないでしょうか。その点について興味のある方は以下の本が役に立つかもしれません。いずれも新書です。
・小沢牧子『「心の専門家」はいらない』洋泉社、2002年。
・小沢牧子・中嶋浩籌『心を商品化する社会 「心のケア」の危うさを問う』洋泉社、2004年。
・ライフヒストリーの研究を読んで、個人的なことを社会的現象として位置づけていいのかという疑問をもちました。また、研究者の主観で、導き出される結果が変わることがありえるのはどうなのでしょうか。研究者がそうなってほしい結論に操作されてしまうことはないでしょうか?
→個人的なことはしばしば社会的なことなのです。もちろん人間が経験することがらは、それぞれの人にとってはいずれも個人的なことがらです。しかし、たとえば失業や単身赴任、結婚などはきわめて個人的なできごとである一方で、経済構造や就業構造、社会構造によって大きく影響されている社会的な問題でもあります。ミルズという社会学者は、私的な問題と社会的な問題との結びつきを見出すことが「社会学的想像力」なのだと言っています。
また、研究者の主観で導き出される結果が変わるのではないかという問題ですが、正確には、得られたデータが、それまでの研究者の解釈を変えたということになると思います。それは、研究の途上ではごく当たり前のことですし、物理学や化学の研究でも同じことが生じるでしょう。結論の操作は、どの学問分野であっても、不誠実な研究者であればやりかねない問題です。それに対し誠実な研究者は、どの学問分野であっても、結論に至ったデータや経緯をきちんと示しながら、自らの解釈の妥当性について説得することになるでしょう。
では、また次回お会いしましょう!!
 |
記:2004年6月28日
1週遅れの更新となってしまい、申し訳ありません。今回は、学校では子どもたちに何を教えているのかを考えました。
課題論文で指摘されていたのは、算数という、ある一定のルールに基づいた営みの学習が、どのようなルールに基づいて営まれているのかが重要であるということでした。
つまり、ある言語ゲームを習得する学習が、どのような言語ゲームに基づいているかによって、習得のされ方が異なるというのです。
たとえば、民主主義という、ある一定のルールに基づいた営み(言語ゲームA)について、非民主的で独裁的に営まれている学習(言語ゲームB)を通して学ぶならば、民主主義はどのようなものとして学ばれるでしょうか。その場合、民主主義の理念や意義について納得がいくものとして学ぶことができるでしょうか。あるいは、民主主義を体現していく主体として育っていくことができるでしょうか。
算数も同じことです。算数の世界ではそう決まっているのだから、ただ覚えればいいんだという言語ゲームのなかで、算数という言語ゲームを学ぶ場合と、たとえば、算数という言語ゲーム自体がどんなふうに成り立っているのかを探究していくような言語ゲームの中で学ぶ場合とでは、算数に対する理解が異なってくるでしょう。算数の理解の仕方が異なるにとどまらず、学習とはどのような営みなのかということに対する理解の仕方も異なってしまうかもしれません。
子どもたちは、学校の算数の時間に、算数という言語ゲームの内容を学んでいるだけではなく、その授業が基づいている言語ゲームからもさまざまなことを学んでいるのです。
では、次回の課題は次の文献です。教師の人生や生活について考えます。
・アイヴァー・F・グッドソン『教師のライフヒストリー』晃洋書房、2001年、第5章。
・松平信久・山崎準二「教師のライフヒストリー」佐伯胖他編『岩波講座現代の教育6 教師像の再構築』岩波書店、1998年。
・紅林伸幸「教師のライフサイクルにおける危機 ―中堅教師の憂鬱―」油布佐和子編『教師の現在・教職の未来』教育出版、1999年。
では、今回のリアクションペーパーを紹介します。
・現場ではいま必死になって、自分で考えて行動できる子どもを育てようとしています。しかし、教師の教授法次第では、子ども自身が考えたり学んだりする機会や場を失わせてしまうのだなと実感してしまいました。
→その通りですね。教師が教えようとしていることと違っていること、場合によってはまったく正反対のことを、生徒たちは知らず知らずのうちに学んでいるなんてこともあるでしょう。退屈な授業では、忍耐力を学んでいるのかもしれませんし、先生が課題をたくさん出してくれる授業では、課題とは自ら見つけるものではなく与えられるものということを学んでしまっているのかもしれません。授業自体がどんな言語ゲームになっているのかが重要なのですね。
・意味も考えずに答えだけをひねり出すという算数を教えてしまっているという学校の状態は、学校を包み込んでいる社会自体が、「成果主義」を奨励していることを考えると、学校が悪いというよりは、いたしかたのないことのように思われます。
→なかなかするどい意見です。社会→学校という向きの影響力が働いていることは否定できません。それだけを考えるなら、確かに「いたしかたのないこと」なのでしょう。しかしその一方で、学校→社会という方向のベクトルを考えることもできます。たとえば、子どもを教育することで社会を変えていく原動力として学校をとらえようとする立場は後者の方向の影響力を重視するでしょう。終戦直後など、民主的な社会の建設にむけて、学校に大きな期待がかけられていた時代もありました。このような立場からは、「いたしかたないこと」では決してなく、もっと学校にしっかりしてもらわないと困るという意見が出てきそうです。
・算数の中では、「1+1=2」という命題が絶対的に信仰されています。しかし、「1+1=1」の場合や「10?」の場合、「1+1=1+1」の場合があると思います。これらは「でたらめ」であるということできますが、全て「ある条件下」で成り立ちます。例えば、会議室の蛍光灯は何本かという問いに対して、2本組みを一つと考えると「1+1=1」です。また、このような簡単な問いに対しても揃えておかなければならない前提(例えば、切れた電球も一本と見なすとか)があります。しかし、そういうことは算数の授業の中で取り上げられることはありません。学校算数とは、一種の前提の上に立脚した「特殊な言葉のやり取り」であるのです。
このときに、思い出したのが、学校になじめず、母親に教育してもらったという伝説がある有名なエジソンです。子どもだったエジソンは教師の言うことが分からなかったし、教師もエジソンのいうことを理解できなかったと言うことが、この言語ゲームの話に近いのではないかと思いました。教師は、「普通」の子どもなら分かるはずのことが、エジソンはその前提そのものを問うために、かみ合わなかったのではないかと思います。教師とエジソンは、プレーしている言語ゲームが異なっていたということかもしれません。
ここで、教師をエジソンの気持ちを分からないひどい教師だったと責めるつもりはなく、教師とはそういうものであるという事実の方が大事なのではないかなと思います。教師は、社会の中で流布している言語ゲームを教室の中でも行うことで、社会の中で生きる訓練をしているのではないでしょうか。その社会とは、それぞれ違っているものも物体として同質視してカウントし、効率性を上げる産業社会かもしれませんし、「0」と「1」の情報社会かもしれませんが・・・。
→今回はリアクションペーパーを書く時間がほとんどとれなかったこともあり、メールでリアクションしてくださいました。どうもありがとうございます。とても分かりやすい例を出して、今回の難解な論文の要諦を説明してくださいました。教師は、学校という場に特殊な言葉のやりとりを教えており、それは近代社会の要請なのであるという指摘はまさに慧眼です。教師に必要なのは、そうなってしまっていることの自覚と、近代社会の要請を生活者の視点へとずらしていくことなのかもしれません。
では、また。
記:2004年6月16日
今回は、学校は生徒たちにとってどのような場になっているのかを考えました。
学校で受ける評価に対しどう対処するかによって、子どもたちがいくつかのタイプに分かれていることが分かりました。タイプの異なる生徒には、学校の意味も異なっているのかもしれません。
また、学校は多くの生徒たちにとって、学校外の若者文化(コギャル文化)と接触するチャンネルとして機能しており、若者文化との接触は、新しい自分への変貌と、友だちとのつながりをももたらしていました。
学校は、期せずして、さまざまなアイデンティティを子どもたちに付与していく場になっており、生徒たちを学校がどのように処遇するかによって、それぞれの生徒の身につけるアイデンティティが異なっているのです。
次回は以下の文献を課題にします。学校では何を教えているのかがテーマです。なお、内容がけっこう難解なので、課題の論文は2本だけです。しかし、上野論文で用いられている「言語ゲーム」という概念を理解するのに役立つと思われる参考文献も挙げておきますので、そちらも読んでおいてください。
・上野直樹「学校文化の言語ゲーム 上・下 ―教育への状況論的アプローチ」『児童心理』第48巻第2号、第4号、1994年。
・<参考>橋爪大三郎『」心」はあるのか』ちくま新書、2003年、78-112頁。
・<参考>田辺繁治『生き方の人類学 実践とは何か』講談社現代新書、2003年、47-64頁。
・佐伯胖「考えること・学ぶこと」天野郁夫編『教育への問い』東京大学出版会、1997年。
では、みなさんのリアクションペーパーからいくつか紹介します。
・生徒同士による相互悪評効果によって、ますます生徒が悪くなっていくという話だったが、それは生徒間のみならず、教師の間にも存在するのではないか。いわゆる底辺校に勤めている友人の話だと、「職員の間でも、どうせこの学校の生徒だからという感じであきらめがある」とのことだった。相互悪評効果の悪循環を断ち切るためには、まず教師自身のそれを断ち切る必要があるだろう。
→教師が生徒をどのような存在とみなすかによって、生徒のありかたが影響されることは十分に考えられるでしょう。前に読んだ論文の「ラベリング効果」というやつです。最近はやりの「コーチング」でも、相手を「未熟」で「できない」存在としてではなく、「できる存在」「向上したいと考えている存在」として見なすことから始めるそうです。学校では、「できる存在」として生徒を見なすことのできる、教師と生徒の双方にとって不満のない地点をどこに見つけることができるのか、教師が率先して探していく必要があるのかも知れません。
・相互悪評効果にしても、学校内におけるコギャル文化の形成にしても、結局は、階層を形成するという論理に行き着いている。コギャルたちの「オタク」に対する視線は、かつて彼女らが受けてきたものと同一なのだろう。そう考えると、つまるところ学校は、彼女らに差別の論法を教えたことになる。学校は子どもを「社会化」するとは、そのようなものではないはずなのに。
→子どもは、自分がされてきたような仕方で他人に対峙するのでしょう。劣位に置かれてきた子どもたちが、いざ優位に立って自分たちの社会を形成するときには、やはりそれまでにされてきたようなやり方で、劣位の相手に対処するのでしょう。意図するとしないとにかかわらず、学校ではそのようなやり方も教えてしまっているのですね。社会を作るには、もちろん別のやり方だってあるはずだと思うのですが。
・評価を受けるということが、評価の本来の目的とは異なった作用を子どもに及ぼしているという点に留意すべきであろうと考えた。教師がなす評価が子どもを成長させるということが単純に語られすぎなのではないだろうか。
→「こうなるだろう」という希望でもなく、「こうするべき」という当為論でもなく、意図せざる結果をも含めて、ありのままの現実の姿を探究しようというのが社会学の基本的なスタンスです。その現実を踏まえるところから、現実に対する新しいアプローチの仕方を考えていくようにしたいものです。
じゃあ、また次回! (^^)/
記:2004年6月9日
今回は、教師の行為について考えました。
教師の行為を、教師自身が学校でなんとかやっていくためのストラテジーとしてとらえた論文を検討しました。このとらえかたは、教師の行為を「教師自身のためのもの」として分析することでもあるのです。しかし、そういった側面は、しばしば見逃されがちです。
日本の教師たちは、子どもをコントロールしたり、規範を身につけさせたりするために、ラベリングや仲間はずしといったストラテジーを用いていることが分かりました。しかし、意図せざる結果として、ラベリングや仲間はずしというやり方そのものを子どもたちが学び、友だち同士のなかで使用してしまっていました。いじめにつながる人間関係の構築の仕方は、学校が教えているのかもしれません。
教師の用いるストラテジーがどのような「隠れたカリキュラム」となっているのかを考える必要がありそうです。
今回は、いろいろと活発に意見が出て、議論がおもしろかったように思います。
次回の課題は次の通りです。児童・生徒にとっての学校について考えます。
・金子真理子「教室における評価をめぐるダイナミクス ―子どもたちの行動戦略と学校適応―」『教育社会学研究』第65集、1999年。
・上間陽子「現代女子高生のアイデンティティ形成」『教育学研究』第69巻第3号、2002年。
・門脇厚司「高校における相互悪評効果」門脇厚司・陣内靖彦編『高校教育の社会学』東信堂、1992年。
では、今回のリアクションペーパーを紹介します。
・幼稚園でのラベリングが日本的集団主義規範の形成に影響するなら、たとえば、アメリカではこのようなラベリングが行わないということだろうか。
→アメリカでも、もちろん何らかの形でラベリングが行われているのは確かです。しかし、それがどのようなやり方でなされているかという点において違いがあるのではないでしょうか。少なくともアメリカでは、日本の学校のように児童生徒全員に同じことを一斉にやらせ、その集団行動に合わせられない子どもを際立たせるというやり方はとらないでしょう。そういったやり方をするところにこそ、日本の特性があると分析されていたように思われます。
・教師が理想像を抱くことは大切だが、それに子どもが近づくことよりも、子どもがその理想像から抜け出したときに本当の喜びを感じるように思う。
→その通りだと思います。しかし、自分の抱いている理想像からの逸脱を是認したり、意味づけたりすることはなかなかできることではないでしょう。私たちはどうしても、理想像を絶対化してしまいがちだからです。自分の抱く理想像をも相対化できるメタな視点をもてるようになりたいものです。
・教室の教育目標や学級目標の横には、「みんな違って、みんないい」と掲示しています。子ども一人ひとりの個性を児童だけでなく、教師も含めた全員で認めていこうという意図で貼られていると思います。しかし、みんなの違いを認めない今日の幼稚園のラベリングの話から、教室とは矛盾することがたくさんある場所なんだなと考えさせられました。
→そのような矛盾の中で、金子みすゞの言葉はどのような意味を持ってしまうのでしょうか。「美辞麗句は信用するな」というメッセージとなってしまうのかもしれません。あるいは、「学校はしょせん偽善的な場所」というメッセージでしょうか。そこまで至らないとしても、少なくとも「みんな違って、みんないい、とは限らない」ということは伝わってしまっているように思われますが、いかがでしょうか。
・学校において、教師の言動はすべて戦略であると思うし、また戦略であるべきだと思う。そもそも、人間関係には必ず戦略が存在しうると思うのですが…。
→意識するとしないとにかかわらず、戦略的に行為しているのかもしれませんね。しかし、ある目的を達成するためのものとして、戦略概念が用いられていることに注意してください。つまり、行為を戦略としてとらえるだけでは不十分で、戦略的な行為がどんな目的のためのものなのかを考える必要があるということです。
では、また次回お会いしましょう。
 |
記:2004年5月31日
前回につづき、今回も日米比較によって両国の学校文化について考えました。
規律の厳しいアメリカ合州国の学校と緩い日本の学校、作文指導で型を重視するアメリカ合州国と自由に書かせる日本など、両国の実際は一般的なイメージとは異なっていることが分かりました。
また、多文化教育においてはさまざまな「資源」が活用されており、それらの資源の配分の仕方に両国の違いが見られるようです。それは必ずしも多文化教育に限らず、通常の授業にも当てはまることではないかという議論も出ました。
外国との比較という方法によって、私たちが日頃行っていることがすべてではなく、別の考え方や別のやり方があることがよく分かります。また、なぜ自分たちはそのようにしているのかを考えることで、自分自身をしばっている見えないルールを自覚化することもできるでしょう。そのようにして、これまでとは異なった実践を創造してくださることを期待しています。
次回の課題は以下の通りです。児童・生徒に対する教師の行為について考えます。
・久冨善之「生徒−教師関係と教員文化」久冨善之編『日本の教員文化 ―その社会学的研究―』多賀出版、1994年。
・結城恵「社会化とラベリングの原初形態 ―幼稚園における集団カテゴリーの機能―」『教育社会学研究』第55集、1994年。
・清水睦美「教室における教師の『振る舞い方』の諸相 ―一教師の教育実践のエスノグラフィー―」『教育社会学研究』第63集、1998年。
では、みなさんのリアクションペーパーをいくつか紹介しましょう。
・型重視の日本が、作文指導ではそうではないというパラドクスになるほどと感じた。齋藤孝氏が、戦前の教育の過度の反省から、教育現場で型を教え込むことに抵抗感が強いのではないかと述べている。型を型として自分のものにしてこそ独創的なアイディアも出せるのではないだろうか。
→齋藤さんの言うことも分かるのですが、型とはどのようなものかがきちんと分かっていないと、困ったことになってしまうこともあるようにも思うのです。というのは、作文の内容を紋切り型にすることが「型」を教えることだと誤解されてしまうと、思想の統制につながってしまいます。ですから、かなり慎重に行うべきだと感じます。余談ですが、齋藤さんは私の結婚式で乾杯の音頭をとってくださいました。
・自分が当たり前だと思っていることを何かと比べることで見直す機会を持つことの重要性を感じています。人から見ればとっぴなことを思っているのではないかと臆してしまっている人の考え方こそ、他の人にとっては重要なものかもしれません。
→その通りだと思うのですが、悲しいことに、私たちは自分とは異なる視点からものを見ることがなかなかできないですし、さらに悪いことに、自分とは異なる視点からものを見る人を疎ましがったり、排除したりしてしまいがちです。異なった意見を大切にしようと言ったり、個人個人の心構えを変えていきましょうと言ったりするだけでは改善されません。異なった意見も言える仕組みやシステムをどう作るのか、異なった意見が大切にされている場にはどのような仕組みが備わっているのか、というように問いを立てていくことが有効ではないでしょうか。
・マイノリティ側に横並びを押しつけるという「平等」に対して、公正という視点が大切であることが分かりました。
→外国との比較という相対化によって、横並びの平等を押しつけるという「見えないルール」に従っていた私たちの姿が見えてきました。文化を問うことは、見えないルールによる拘束から自分自身を解放することでもあるんですね。
では、また!!
記:2004年5月26日
今回は、日米の比較によって、両国の学校文化について考えました。
活動が一斉的に活動が行われる小学校の教室が、問題をはらむものとして分析される一方、子どもたちがのびのびと育まれているものとして分析されていました。どういう観点から分析するかによって、同じような教室が違ったものとして見えてくる好例だったように思います。しかし、どちらの論文でも、授業その他の活動が子どもたちが同質的であるという前提に立って組み立てられているところに焦点を合わせていることが共通していました。
また、日米の教師がどのように授業をするかは、動機づけに関する考え方の相違に影響されており、動気づけに関する考え方の相違の背後には、学校組織の構造の違いが横たわっていることが分かりました。
このように、自由に振る舞っているように考えている私たちの行為は、子どもに関する前提や、学校組織のありかたといったことがらに制約されたものなのです。
課題として読んでいる諸論文の知見に賛同する、反対するといったレベルだけではなく、それらの論文が何に注目してどう分析しているか、どのような構造で論を組み立てているか、問いと方法がどう組み合わされているか、先行研究の検討をどう行っているかなどなど、「メタ」な読み方もしてみてください。
次回も引き続き日米比較から考えます。課題は次の文献です。
・臼井博『アメリカの学校文化 日本の学校文化』金子書房、2001年、230-279頁。
・渡辺雅子「作文指導に見る個性と創造力のパラドックス ―日米初等教育比較から―」『教育社会学研究』第69集、2001年。
・額賀美沙子「多文化教育における『公正な教育方法』再考」『教育社会学研究』第73集、2003年。
では、リアクションペーパーを紹介します。
・教師と生徒の人間関係に頼ってしまっている指導は危険ではないか。もちろん人間関係は大切だが、それに頼って本来指導すべき専門性を高めるという点で甘えが出てしまっているような現状があるように思う。
→生徒と教師の人間関係ができてるから、授業がつまらなくてもなんとか聞いてくれる、ということだと本末転倒ですよね。でも実際、ご指摘のように、そうなってしまっていることもあるのでしょう。また、人間関係が実際に重要だから、教師たちが人間関係を重視するようになるという因果関係だけではなく、教師たちが人間関係を重視するから、人間関係が実際に重要になってしまうという逆の因果関係も成り立ちうるかもしれません。2つの因果関係が互いに補強しあっているのが現実かもしれませんが、私は後者の比重が高いのではないかとも感じています。いかがでしょうか。
・今回の論文を読んで、アメリカの先生が「自分のクラス」と言ったとき、何をイメージするのだろうかと思いました。教師とteacher、学級とclassなど、同じと思って使っている言葉も、実はあらわしている内容が違うのかもしれないと感じました。
→その通りですね。相手がユニークなのか、それとも私たちがユニークなのか、どちらなのでしょうか。たいていは自分たちを基準にして相手がユニークだと考えてしまいますが、相手を基準にして自分たちがユニークだと考えてみてください。そうすることで、自分たちのユニークさはどんなユニークさなのか、どうしてそうなのか、そのユニークさは私たちに何をもたらしているのかなどなど、いろいろおもしろそうなことが見えてくるかもしれません。
・勉強したらピザの無料券をあげることもあるというアメリカの例が出てきました。日本では、学習に「ごほうび」をあげるのは不道徳だといういい方がなされますが、私は、学習への「対価を支払う」というアメリカ型の考え方に親近感を覚えます。「ごほうび」をあげるというのは、子どもを低く見ているから出るいい方だと思います。
→それに加え、こんな考え方はどうでしょうか。つまり、学校での学習はどこかしら「神聖なもの」であるという考え方です。学校での学習を、対価を要求してはならない特別な活動とみなしているからこそ、ご褒美や対価を介在させることはタブー視されるのかもしれませんね。
では、また次回!
記:2004年5月17日
今回は、言説分析という手法によって、歴史的に学校や教師をとらえた論文を読みました。人々が学校や教師に注ぐまなざしを検討することで、学校や教師のありようをとらえ直そうとするものでした。
人々が教師に期待する役割が時代によって異なっていることが分かりました。そうだとすれば、現在の私たちが「これが教師の役割」と考えているものも唯一・絶対・不変なのではなく、現代という時代や社会のなかで作られているものなのです。
現代における「カウンセリング・マインド」や、「学校と家庭との関係」についても、時代や文化の産物として一歩離れたところから相対化してみることで、自分たちのしていることを反省的にとらえなおし、新たなものへと組み替えていくきっかけをつかむことができるのではないでしょうか。
次回までの課題は次の通りです。次回は、学校や教師について日米比較を通して考えます。
・酒井朗・島原宣男「小学校教師の指導観に関する日米比較 −動機づけに関する考え方の違いに注目して−」南山大学『アカデミア』人文・社会科学編(64)、1996年。
・恒吉僚子「教室の中の社会 −日本の教室文化とニューカマーの子どもたち」佐藤学編 『教室という場所』国土社、1995年。
・ナンシー・佐藤「日本の教師文化のエスノグラフィー」稲垣忠彦・久冨善之編『日本の教師文化』東京大学出版会、1994年。
さて、今回のリアクションペーパーをいくつか紹介することにしましょう。
・今回の論文では新聞記事を取り上げていたので思い出しましたが、テレビニュースで「昨年まで夏休みは遊んでいた教師が、今年から遊べなくなりました」とレポーターが話して市民に意見を聞くという番組をやっていました。また、幼児を突き落として死なせた中学生について、さんざん「障害を持った少年が…」といっておいて、最後に「この障害を持っているからといってこのような事件を引き起こすわけではない」とつけ加えていました。報道が世間の人々に誤った考え方をすりこんでいると思い、視聴者としてはただ与えられるものとして見てはいけないと感じました。
→そのとおりですね。テレビで流されている情報は人々への影響は大きいにもかかわらず、不確かな情報を伝達したり、生放送で無責任な発言を垂れ流したりしており、テレビにはとても問題が多いと思います。その問題性を指摘することに加え、テレビがあなたの指摘なさったような見解を垂れ流す背景には、教師や非行に関する、人々のどのような見方や考え方があるのかを問うのが言説分析です。そうすることで、単にテレビのせいだという犯人捜しにとどまってしまうのではなく、自分たち自身の問題としても考えることができるようになるでしょう。
・今日いちばん印象に残ったのは、教師が「生徒理解の時間」などを設けて生徒の理解を深めますといったことを、生徒側は冷ややかな目で見ているのではないかというお話でした。生徒を理解しようとする行動を起こすこと自体が生徒を理解していないことだという不思議な矛盾を感じました。
→どうしてそうなってしまうのか、そこにはどのような仕組みがあるのか、とても興味深い問題ですね。そのような矛盾は、児童や生徒を理解しようというところばかりではなく、教師の行動におけるその他のさまざまなところにも見てとることができるのでしょうか。何か考えついたらお知らせください。
・年配の先生方から、若い時の苦労話や自慢話を聞かされ、「大変だったんですねー」と単純に感心していましたが、その当時としては当たり前のことだったんだと気づきました。私たちも「忙しい」とか「大変だ」とか言いながら、今が「普通」だと思っているわけです。
→とても重要なことに気づきましたね。私たちの考えている「普通」も、私たちがそう考えているに過ぎないのだとしたら、私たちの「普通」は、どんなふうに「特殊」、あるいは「変」なのか、私たちの「普通」はどんなふうに作られているのか、私たちはどのようにそれを「普通」だと思いこまされているのかなどなど、さまざまな問いが浮上してきます。私たち自身の文化を問い直すとはそのような作業なんですね。
・今回の言説分析からは、結局のところ、教育の世界とは自らが大きく変化させることができるものなのではなく、社会や環境の変化などで変化していくものなのだと改めて感じました。主体的・能動的な世界なのではなく、受動的な世界なのだと悲観してしまいました。
→悲観してしまうと、今回の諸論文の真意を誤解してしまうことになります。というのは、今回の諸論文は、私たちの受動性(=被拘束性)を理解することが、主体性・能動性(=拘束からの離脱)へのきっかけとなりうるという前提に立っているように思われるからです。それに加え、これらの論文で言われていること自体も「言説」であることを忘れてはいけません。
では、また!
記:2004年5月6日
今回から、課題となった論文に関する議論を通し、学校や教育の文化について考えていくことになります。今回の課題は、歴史を振りかえることによって文化をとらえ直そうとする論文でした。
私たちが当たり前のものと考えている学校は、近代に特有のものであり、それを自覚して議論する必要がありそうです。
また、教師が現実に直面している困難の本質や、学校や教師の問題として語られていることの本質は、実は学校だけを見ていたのではとらえることができないようです。
さらに、現在の学校を作り上げている道具立てや、それに基づいた行動様式は、文化的に作られたものだったことも分かりました。
学校や教育を歴史的に相対化してみることで、学校や教育を複眼的にとらえる視点を得ることができたのではないでしょうか。
課題の諸論文を読み、それらについて議論をすることによって、みなさんのこれまでの学校観や教育観を問い直し、新しいものへと自分なりにつくりかえていっていただけるならば幸いです。
さて、次回までの課題は次の通りです。
・油布佐和子「7章 教師は何を期待されてきたか」油布佐和子編『教師の現在・教職の未来』教育出版社、1999年。
・広田照幸「学校像の変容と〈教育問題〉」佐伯胖他編『岩波講座現代の教育 第2巻 学校像の模索』岩波書店、1998年。
・酒井朗「”児童理解”は心の理解でなければならない −戦後日本における指導観の変容とカウンセリング・マインド」今津孝次郎・樋田大二郎編『教育言説をどう読むか』新曜社、1997年。
では、みなさんのリアクションペーパーを一部紹介します。
・課題の論文を読んで、教育問題の責任の所在は一体どこにあるのか。何を解明することが必要なのか悩んでしまいました。
→どこかに責任を負わせるというやり方は、システムの諸要素のうち、どれか一つの要素が悪いと考えることでしょう。その場合の改善策は、悪いとされる要素を改めるということになります。しかし、諸要素同士を結びつけるやりかたが悪いとすれば、それぞれの要素が悪いわけではないことになります。そうなると、要素を改めるという改善策はとれないわけです。後者の場合、要素を改めようとするような思考の枠組の中でいくら考えてみても袋小路に入ってしまうことになるでしょう。それと同じように、今の私たちに必要とされるのは、これまでの思考の枠組を越える新しい発想なのかもしれません。
・論文で問題だとされていることは本当に問題なのかという、自分の発想にはない意見も聞くことができてよかった。ただ、やはり社会が分業化していく弊害に危機を感じ、それを食い止める努力をしてきたからこそ、そのような意見も可能なのかもしれないというような気もします。
→自分の発想にはない意見を聞くことで、自分の意見を深めることができたようですね。理解を深めるための議論という、この授業で目標としていることが実践されているようでなによりです。今後も、活発な議論のできる論点が出てくることを期待しています。
・大学院に来て、大きな視点で社会の仕組みそのものを見直してみようという観点に立つことが多くなったような気がします。そのおかげで今まで見えなかったものが見えもするのですが、逆に、何が正しくて何が正しくないのか、といった根本的な部分が揺すぶられて、何がなんだかよく分からなくなってきました…。
→それは、とてもいい経験をしているということではないでしょうか。そういうところをくぐり抜けてこそ、借り物ではない自分自身の考えを手に入れることができるように思います。
では、また。(^^)/~~
記:2004年4月22日
学校文化特論の第2回目でした。今回もまた、私のほうからお話をするという形ですすめました。
今回はまず、空気のような存在としてほとんど意識しない文化について、身近な例によって意識化してみました。学校をめぐる自分にとっての「当たり前」は、他人にとっての「当たり前」であるとは限らないことが理解できたのではないでしょうか。私たちの学校体験も、「文化」として形作られていたものだったのです。
続いて、文化のとらえ方について、視点、手法、立場という3つの点からお話ししました。それら3つの点が異なれば、とらえようとする文化もまた違うものとなってくるのです。
最後に、教育や学校の文化に着目した研究の知見の一端をお話ししました。一つは、文化の内容という観点から、学校で伝えられる知識や技能をとらえた研究です。もう一つは、文化の型という観点から、文化の内容の伝達方法について検討した研究です。これらの研究からは、今までとは異なった学校や教育の姿が見えてきたのではないでしょうか。
次回からは、課題論文の議論を中心にした授業となります。教材開発室にマスターコピー(昨年度までとは異なり、教材開発室の机の引き出しの中にあります)を置いておきますので、それを利用してください。議論が活発なものとなるよう、よく読んできてくださるようお願いします。
なお、次回までの課題論文は次の3つです。
・寺崎弘昭「歴史のなかの教育」天野郁夫編『教育への問い』東京大学出版会、1997年。
・矢野裕俊「教室の道具立て」石附実編『近代日本の学校文化誌』思文閣出版、1992年、69-94頁。
・宮澤康人「学校を糾弾する前に ―大人と子どもの関係史の視点から―」佐伯胖他編『学校の再生をめざして1 学校を問う』東京大学出版会、1992年。
では、今回のリアクションペーパーの一部を紹介します。
・文化の違いは、価値観の違いに発展すると思う。そのため、文化の違いを理解するためには、いくつかの文化を多く体験することが大切だと思った。
→その通りですね。私たちは、自分の文化が優れていると思ったり、自分の文化以外のものを肌が合わないと嫌悪したりしてしまいがちです。それを緩和するためには、さまざまな文化を実際に体験してみたり、自分とは異なった文化を大切にしている人々と出会ったりすることが役に立つことでしょう。しかし現実には、必ずしもたくさんの異文化と出会えるとは限りません。その一方で、異文化に出会っていても、気づかないで過ごしてしまっているのかもしません。どのようにして異文化に対する私たちの感受性を高めていくのかは、重要な問題ですね。
・学校の文化も地域や国によってとても差があることがよく分かった。また、中央の文化に合わせて示されていたということも分かった。きっとまだ自分の知らないところでいろんな影響を受けていることだと思う。
→異文化に気づくことよりも、自分の文化に気づくことのほうがもっと難しいのかもしれません。この授業を通して、自分の文化が自分自身の思考や行為を拘束していることに目を向けていきたいものです。それは、自分を拘束から解放するという前向きな作業である反面、それまでの自分の硬直性を直視する不愉快な作業でもあります。しかしそれを乗り越えて、できるだけ柔軟で軽やかな人間になりたいものです。
・学校で扱う内容がエリート文化であるのは、それを決定する人々がエリートだからなのでしょうか? それともエリート志向だからでしょうか?
→学校で教えるべきことがらを決めている人たち自身はあまり自覚はないかもしれませんが、やはり彼らは「エリート」だと言えるでしょう。子どもたちにとって、学校で教えることは「正しいこと」だったり、「よいもの」だったりするわけですから、子どもたちは知らず知らずのうちに、エリート文化こそが正しいものであり、よいものであるということを学んでいっているわけですね。
では、また次回お会いしましょう。
記:2004年4月16日
学校文化特論の講義がいよいよ始まりました。みなさんどうぞよろしくお願いします。
今回は、講義のイントロダクションとして、文化をどうとらえるか、文化という視点から考えることの利点、学校文化に注目するようになった理由、といったことについてお話ししました。
学校文化に着目することは、あるがままの学校の姿とその背後にある仕組みやルールをとらえなおし、新たな学校を創り出していこうとすることです。
ものごとをよりよく理解するための「イシューをめぐる議論」によって、学校文化に関する理解を深めていきましょう。
では、また次回。
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Copyright(c)2004 FUJITA Takeshi. All Rights Reserved. |
|

|
|
 |