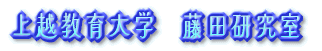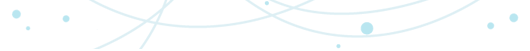|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
「反差別の授業の構築に向けて ―『青い目 茶色い目』の授業の社会学的考察をとおして―」
日本教育方法学会編『教育方法学研究』第21巻、193〜201頁、1996年3月(単著)。
本稿では、反差別という生活態度の育成にむけた指導の方法について考察した。
従来の反差別の教育では、子どもに反差別の意識を持たせることが目標とされていた。しかし、多くの場合、差別していることに気づいていなかったり、差別はいけないと知っていても差別してしまったりと、反差別意識の教育が差別行為を食い止めるとは限らない。つまり、考察すべきなのは差別意識ではなく、差別行為なのである。したがって本稿では、米国で行われた反差別の実験授業の記録を手がかりにして、他者との対面状況における差別行為の仕組みを分析し、差別行為を食い止める教育方法を提起した。
実験授業を手がかりにした差別行為の考察からは、次の五つの点を明らかにした。第一に、対面的状況における差別行為は、人種や性別など相手との差異を認識すると同時に、相手に対して自分とは異なったルールを適用することによって生起しており、それは第二に、差別する側によって一方的に決定されており、差別される側の都合や意見は排除されている。第三に、さまざまな差別行為の仕組みは、差異を認識するかどうかと、異なったルールを適用するかどうかという二つの軸を組み合わせることによってとらえることができ、第四に、そのような仕組みを持つ差別行為と、差別的ではない通常の相互行為は、実は同一の仕組みから成り立っている。第五に、我々は無意識のうちにその仕組みにしたがって相互行為を行っているため、そもそも差別行為へと陥りやすい傾向を持っている。したがって、反差別意識を持っていたとしても気づかぬうちに差別行為に陥ってしまう原因の一端は、我々の相互行為の仕組みにあるのである。
上記のことから、反差別の教育を構築するために重要な点として次の三つを指摘した。第一に、反差別の意識を子どもたちに教えるだけでなく、気づかないうちに差別してしまう相互行為の仕組みを理解させるとともに、その仕組みに通常の行為が拘束されていることに気づかせることが肝要である。第二に、その拘束を抜け出すためには、差別してしまう自分への感受性を高めさせ、自分自身の行っている相互行為のありようを自覚化させるように促すことが必要である。その一方で、第三に、子どもたちを教える側についても、子どもたちの都合や意見を排除することがないように自らの行為を自覚化しなければならない。
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Copyright(c)2004 FUJITA Takeshi. All Rights Reserved. |
|

|
|
 |