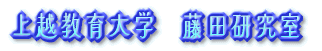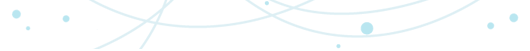伊藤秀昭
「小学校における教師の秩序維持に関する研究 ―3人の教師の児童に対する働きかけを手がかりにして―」
(上越教育大学修士論文)
1.問題の所在
教師たちは、子どもとの間に良好な人間関係を築くことと、制度的に不可避的な対立関係構造の中で権威を保持しながら指導していくことのジレンマを実践的に解決しながら、ごく当たり前の学校の日常を滞りなく成り立たせている。
しかし昨今、「学級崩壊」がクローズアップされ、「教師の指導力不足」と考えられる事例の割合が高いと報告されている。そうだとすれば、教室の秩序が当たり前に成立していること自体に改めて焦点をあて、教師たちがその当たり前の秩序をいかに維持しているのかを問い直すことが必要ではないか。
そこで、本研究では小学校を対象とし、教師たちが、どのように日常の秩序を維持しているのかを検討することによって、教師と児童のあるべき関係について示唆を得ることを目的とする。
2.本研究の構成(節題省略)
序 章 本研究の主題と課題の設定
第1章 教師による児童のコントロール
第2章 秩序維持の論理と方法
第3章 学習秩序の維持に向けた教師のストラテジー
終 章 本研究の結論と今後の課題
3.本研究の概要
公立小学校において、6学年3学級の担任教師と児童を対象に3ヶ月にわたる観察を行い、筆者が記述したフィールド・ノーツ及び3人の教師へのインタビューをデータとして考察を行った。
第1章では、第一に、教師はその権威を用い、児童の活動や行動について、時間・場所・人・内容・理由・やり方という包括的な側面をコントロールしていること、第二に、秩序は教師と児童との共同作業で作り上げられており、そのようにして成立した秩序だからこそ、継続して維持されていくことを論じた。
第2章では、第一に、必ずしも教師のためだけに児童の発話が抑止されているわけではなく、児童の利益を考えて抑止がなされたり、ある発話がその場の状況にふさわしいかどうかを教えるために抑止されたりしていること、第二に、教師が児童の発話を抑止する方法は、必ずしも教師の権威を一方的、直接的に発動するような方法ばかりではなく、直接的な方法であっても、言い回しを変化させたり、間接的な方法でもさまざまな手法を用いたりすることによって、よりソフトな形で抑止しようとしていること、第三に、発話は、児童の思考を活発にするために促進される一方で、その場を滞りなく次の段階へと進ませるための形式的な材料としても用いられること、第四に、児童の発話を促進するために教師が用いているのは、直接的な方法だけではなく、発話すべき状況の設定、発話の受容、児童同士の相互作用の利用、といった多様な方法を駆使していること、第五に、教師自身も気づかないうちに児童を抑止と促進のダブル・バインド的な状況に陥らせてしまうこともあり、時として、秩序を維持しようとする教師の行為そのものが、秩序を停滞させてしまうことがあること、を論じた。
第3章では、第一に、児童の学習を促進させるべくさまざまな要求をする際に、教師たちは、受容と要求とをセットにするという対立回避のストラテジーを用いていること、第二に、受容と要求をセットとするやり方は、子どもとの人間関係を構築することで対立を回避し、子どもたちの学習を促進させようとする「人間関係構築ストラテジー」として位置づけられること、第三に、学習を促進させるために、教師たちは学習活動をクラス全体のものとして構築し、そこに子どもたち全員を参加させようとする共同学習方式を用いていること、第四に、共同学習方式には、全員がそろったり分かったりすることを確認するというやり方、全員が達成すべき目標や水準を設定しそこに到達するように働きかけるというやり方などのバリエーションが存在していること、第五に、共同学習方式は、クラス集団の教育的達成レベルを均等にすること、集団全体としての達成レベルを引き上げようとすることを意図した「全体的引き上げストラテジー」としてとらえられること、を論じた。
終章では、本研究の知見から得られる示唆について論じた。まず、理論的な示唆として、第一に、教師による秩序維持の目的に関連して、誰のための秩序の維持かという視点の導入の必要性、第二に、行動を促進することで維持されるという秩序観の導入の可能性、第三に、日本の教師という文脈を考慮に入れたストラテジー研究の可能性、第四に、教師の様々な「振る舞い」が複合されて創発的な特性をもったストラテジーに関する考察の可能性、を示した。
また、実践的な示唆として、第一に、児童との人間関係を構築しつつ教師の権威性を有効に機能させることに、教師が関心を向けることの必要性、第二に、「促進の論理」に基づいた秩序の可能性を含めた新たな秩序維持のスタイルの模索と、教師の行動の意味を児童に理解させるための働きかけの重要性、第三に、児童をダブル・バインドの状況に追い込み、かえって秩序を停滞させてしまう可能性など教師の働きかけの影響の認識の必要性、を示した。
4.本研究の課題
第一に、本研究は事例研究であり、知見が必ずしも一般化できるものであるとは限らず、他学年を対象にするなど、同様の研究の蓄積が望まれる。第二に、児童に対する調査データと合わせた考察により、一層教師行動の意味が明確になるのではないかと考えられる。第三に、秩序維持について、教室場面以外のデータに基づいた考察、児童の動機づけという観点から活動内容と関連づけた検討の必要がある。第四に、教師の行動と教師の個人的な要因との関連についての検討も興味深い。
これらの課題を追究することによって、より望ましい教師と児童との関係の樹立に貢献することになるだろう。
|