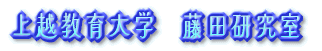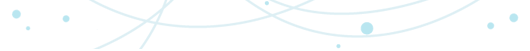栗林正人
「問題行動を抑制する生徒指導体制に関する研究
―荒れた学校をたて直した事例をもとに―」
(上越教育大学修士論文)
1 問題と目的
荒れた学校をたて直す方策はさまざまに主張されているが、荒れた学校は未だになくなってはいない。それゆえ、どのような生徒指導体制が問題行動の抑制に効果的なのか、また、そのような体制を作っていくためには教師に対してどのような働きかけをすることが必要なのかを検討することは、引き続き追究していかねばならない重要な課題である。
そこで本研究では、問題行動が頻発していた、いわゆる「荒れた」状態から学校をたて直すことに成功したA中学校の1年間(平成8年4月〜平成9年3月)を事例として取り上げ、A中学校で行われた実践の具体的な姿と、その実践が基づく考え方を明らかにすることによって、荒れた学校をたて直す生徒指導体制を構築していく方法に関する示唆を得ることを目的とする。
2 本研究の構成
序 章 研究の目的と方法
第1章 A中学校の様子
第2章 教師を動機づける方法
第3章 教師の持つ認知の転換
第4章 荒れた学校をたて直す手法の全体を支える考え方
終 章 結論と今後の課題
3 本研究の概要
当時A中学校で中心人物として活躍していたW教頭にインタビュー調査を行い、そこで得られた語りを再構成することによって当時の生徒指導体制のありようを理解するという方法を用いた。
第1章では、A中学校における生徒指導の実践と、それに伴う教師と生徒の変化を見てきた。
第2章では、A中学校おけるW教頭の実践は、荒れた学校をたて直す取り組みに対して、どのような方法で教師の動機づけを高めようとしたのかを明らかにするため、W教頭が用いた具体的な手法を検討した。これまで多く用いられていた、マイナス点を指摘することで動機づけを高めようとする、いわば「不安喚起型」の外発的な動機づけ方法に対し、W教頭の手法は、安心を与えることによって、自主的、積極的に取り組む姿勢を促す、いわば「安心確保型」とでも言えるような、内発的な動機づけ方法であることを明らかにした。そしてそれは、問題行動を出発点として指導方法を組み立てるのではなく、教師を出発点として指導方法を組み立てていくことでもあるといえる。
第3章では、W教頭は、問題行動を否定的に捉える教師に対してどのように働きかけることで問題解決に向かわせたのか、どのように教師の変化を促したのか明らかにするため、W教頭が用いた具体的な手法について検討した。W教頭の手法は、単なるハウツーの適用にとどまるものなのではなく、さまざまな実践を通じて教師の認知を根本から変えていこうとするものであった。そこで変えようと試みられていたのは、教師、生徒という存在に関する認知、また、教師と生徒の関係に関する認知、さらに、問題行動に関する認知であった。それらの認知の転換を通じて、教師が自らの行動を変え、それが学校を変えることを目指していることが明らかになった。
第4章では、A中学校で実際に用いられた手法全体がどのような考えに基づいて組み立てられているのかについて検討した。W教頭の手法が基づいているのは、よくある学校改善法のように教師を悪者として叱正したり、無能者としてハウツーを覚え込ませたりすることではなく、尊厳を持った人間として尊重することであった。
終章では、本研究の結論とそこから得られる示唆について考察した。まず、理論的示唆として、第一に、教師間の協力体制について共通理解や協力関係の欠如を指摘する以前に、そもそも教師がどのような状況に置かれていて、それが協力体制のありようにどう影響しているのか、実態に基づいた探究をしていく必要性である。第二に、生徒の荒れを関係の問題としてとらえる必要性が示唆される。生徒の荒れは生徒個人の問題ではなく、教師との関係において生じており、もしそうだとすれば、生徒の行動を探究する際には、生徒個人にすべてを帰す「個人還元主義」から、「関係主義」へと見方を転換する必要があるだろう。第三に、教師の尊厳を重視する必要性である。W教頭の用いる手法はすべて、教師を尊重している。学校の仕組みや教師のありようについて探究し、理論を組み立てていくときにも、個々の教師が尊厳を持った存在であることを出発点としていかなければならないだろう。
次に、実践的示唆として、第一に、指導できなくても批判されない雰囲気、いつでもほかの教師が助けてくれる状態、どの教師にも実行可能な指導法など、学校内の制度をそのように組み替えて、教師の安心を確保することが必要となるであろう。第二に、教師と生徒の良好な関係を築くためには、実践を通じて教師を変化させるといった視点が必要である。従来のように生徒だけを変えようとしていたのでは、教師の価値観は変わらず、結局のところ、教師と生徒の対立という構図は変化しないだろう。第三に、生徒指導体制は、即効的なものと時間がかかるものを区別して考えるべきであろう。教師の変化に要する時間がかかる以上、教師に対する働きかけは時間をかけなくてはいけない。しかし一方で、問題行動に対する対応は早急に行わなければならない。このような2つに事態を考慮した上で、生徒指導体制を組み立てていくべきである。
4 今後の課題
第一に、本研究で得られた知見を、荒れた学校で実際に用いていくことによって、さらに新たな知見を獲得していくといった実践的な研究のサイクルを形作っていく必要があるだろう。第二に、教師の尊厳を重視するという考え方は、生徒指導的側面以外では、教師や生徒にどのような影響を与えるのかについて検討していくことが課題であろう。そのため第三に、荒れた学校のみならず通常の学校においても本研究の知見を応用していくことによって、実践的研究を展開していく必要があるだろう。第四に、これからは、学校は生徒だけではなく、教師をも成長させるところであるという考え方に立脚した、新しい学校像というものを描いていく必要があるのではないだろうか。
|