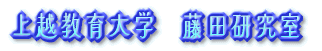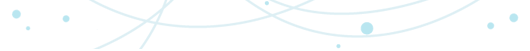山口真希子
「子どもとの出会いによる教師の成長過程に関する研究」
(上越教育大学修士論文)
1 問題の所在
いじめ、不登校、学級崩壊といった問題が学校現場で取りざたされるようになって久しい。そのような問題について近藤(1992)は「教師と子どものミスマッチ」を指摘する。つまり、教師が子どもを見る視点が子どもとかみ合わないときミスマッチが起こり、子どもがはじき出されてしまうという。そうだとすれば、教師が子どもをどう理解するかということが、教育問題を解決に導くための道筋の一つとして考えられる。
子どもを理解することについて、教師たちは「教育実践上の経験」から学んでいると言われているが、教師たちは経験からどのように学んでいるのだろうか。今後ますます教師が子どもを理解しにくい状況になることが予想されるなか、教師として成長を遂げるしくみについて考察することは重要であろう。そこで、本研究では教師としての学びや成長のありようを考察し、日々の実践を自身の成長に役立てるための示唆を得たいと考える。
2 本研究の構成
序 章 本研究の目的と方法
第1章 調査対象者のプロフィールと教職生活
の概略
第2章 4名の先生方の変容
第3章 4名の先生方の成長過程
終 章 本研究の結論と考察
3 本研究の概要
本研究では、成長を遂げた4名の先生方に対するライフヒストリーの聞き取りから、教師が経験から学ぶとはどのようなことで、それはどのような過程で達成されるのか考察した。
第1章では調査対象となった4名の先生方の人となりや教職経験の概略を簡潔に示した。
第2章では4名の先生方の変容を、ライフストーリーを再構成する形で記述した。まず、W先生は子どもへの支援が有効になるにはまず子どもと教師との人間関係ができていることが先決であると考えるように変容した。次にH先生は、子どものありのままの姿をみて、その中に自分と共有できる部分を見つけ「相手を肯定的に受けとめる」ように変容した。さらにT先生は、脱文脈化された知識や技能ではなく子どもに必要な力を考え、子どもの発達段階に応じてその力をつけさせるように変容し、最後にM先生は、一定の基準から子どもを判断するのではなく、できないこととできることに理解を示すような「アバウト」な状態に変容した。
第3章では2章で見た先生方の変容を教師の成長という視点から見たときどのような意味をもつのか、また、どのようにしてそのような変容を遂げることができたのかについて考察し、次のような仮説を得た。
まず、先生方の変容は、自明としていた「〜ねばならない」という強迫的な考えから解放されることであった。すなわち、固定化された教師−子ども関係からの脱却、脱文脈的な知識の教え込みからの脱却、与えられた基準に照らして足りない存在として子どもを見ることからの脱却である。
次に、変容は、当然視していた「〜ねばならない」という考えにとらわれ、教育活動がうまくいない危機的状況、そのとらわれに気づき、自分の教育活動を組織し直すことで危機を乗り越えるというプロセスをたどる。また、危機脱却の際には、危機以前の経験も役立てられていた。この過程は、いわば言語ゲームとしての学校文化の中にとらわれている状態に気づき、そこから抜け出してゲームのルールを自ら作り出そうとする過程であり、その意味において教師自らの主体性を獲得する過程だといえる。
終章では、本研究の結論とそこから得られる示唆について論じた。まず、理論的示唆として、第一に、先生方の成長は経験の量的な蓄積によって達成されたというよりも、経験の質的な転換として捉えることができるということである。第二に、教師の成長に不可欠な省察とは自らを取り巻く自明性を問い直し、そこから抜け出して教育活動を再組織化していく過程であると捉えられること、成長によって信念に対し柔軟になるとは、子どもを主体としてみるという教師が自ら作り出した信念に基づいて、脅迫的な考えから解放されることであることを指摘した。第三には、教師の成長とは、他者との関係の組み替えであると同時に、自らのおかれた状況との関係を組み替えていくことであることを指摘した。
次に、実践的示唆として、第一に、危機こそが好機であると前向きに構えることが危機を成長の契機としやすいこと、第二に危機に対して前向きな構えをもつために、自分が「〜ねばならない」と焦っていることを自覚化する必要があること、第三に危機を乗り越えるために当たり前を問い直し、ルールを自ら作り出すプレイヤーになるため、「あたりまえ」を問い直す機会を設けることが大切であること、第四にそのようなプレイヤーになりやすくするための環境づくりとして、研修の機会を設けるなどして組織的に対応していくこと、最後に、その場において子どものためにという同じ目標に向かって学び合い、高め合っていく仲間との関係を作ることである。
4 本研究の課題
第一にデータの偏りという点についてである。十分に配慮したとはいえ、調査の対象者はいずれも50代女性であるという、年齢的・性別的な偏りがあり、それぞれが既知の間柄であるということがデータの偏りとなって分析に作用したことがあるだろう。
第二に、本研究を今後教育現場にどう生かすかという点である。本研究は現場での疑問から出発した研究であり、現場教育に生かせる研究を目指してきた。今後は、本研究をいかに現場教育にいかすかということが検討課題であると考えている。
|